「登山は若い人の趣味でしょ?」そう思っていませんか?
実は今、60代から登山を始める方が増えているんです・・・。自然の空気を胸いっぱいに吸い込みながら歩けば、心も体もリフレッシュ! しかも無理なく続ければ健康づくりにもつながります。
でも、忘れてならないのは安全装備…。ただし準備ができていれば、不安を安心に変えてくれるんです。本記事では「還暦からの登山」を楽しむための必須装備をチェックリスト形式でご紹介…。さあ、次の週末は新しい一歩を踏み出してみませんか?
登山を始める前に|60代からの挑戦を安全に楽しむために
60代からの登山は、健康づくりにも気分転換にもぴったりです。ですが、60代初心者がいきなり高い山に挑戦するのではなく、まずは標高300メートル前後の低山から始めるのが安心なんです。意外にも低山でも四季の自然を感じられ、達成感も十分なんですよ! ここでは、登山を始める前に押さえておきたいポイントを紹介しますね!
低山スタートがおすすめな理由
📌 登山初心者が最初に挑戦するなら、次のような点から「低山」が安心です。
- 体への負担が少ない:登り下りの時間が短く、筋肉や関節にやさしい
- 安全に慣れられる:道迷いリスクが少なく、途中で下山しやすい
- 自然を楽しめる:季節の花や展望など、小さな山でも十分に魅力的
つまり、低山こそがシニアの登山デビューに最適なステージなんです。
特に注意すべきポイント
登山は「準備」と「安全意識」がすべてと言っても過言ではありません。次の点に注意しておきましょう。
- 体調チェック:少しでも違和感があれば中止する勇気を持つ
- 水分補給:低山でも脱水や熱中症になることがあります
- 靴の確認:滑りにくい靴を選び、靴下も厚手を選ぶと安心
- 時間管理:午後は日が傾きやすいため、午前中に出発するのがおすすめ
- 無理をしない:「疲れたら引き返す」気持ちが安全につながります
初心者が注意すべき登山リスク(低山でも!)
| リスク | 起こりやすい原因 | 予防策 |
|---|---|---|
| 転倒・つまずき | 濡れた岩や木の根 | 靴底のグリップを確認、ストックを活用 |
| 脱水・熱中症 | 水分を我慢してしまう | こまめに少量ずつ飲む |
| 道迷い | 標識を見落とす | 地図アプリ・紙の地図を携帯 |
| 疲労 | 歩きすぎ、無理をする | ペースを落とし、休憩を増やす |
低山だからといって油断すると、思わぬリスクに直面してしまうんです。
ワンポイントアドバイス
標高300メートル前後の低山なんて、大したことないと思われがちですが、60代から始める登山としては、結構しんどく感じると思います。普段体を鍛えていない方は、いきなり1000メートル級に挑むと怪我する可能性が高いので、まずは低山から始めることをお勧めします。
登山は「頑張る」よりも「楽しむ」気持ちが大切です。ゆっくりと自然に触れながら、自分の体調を第一に考えることが何よりの安全策なんです。
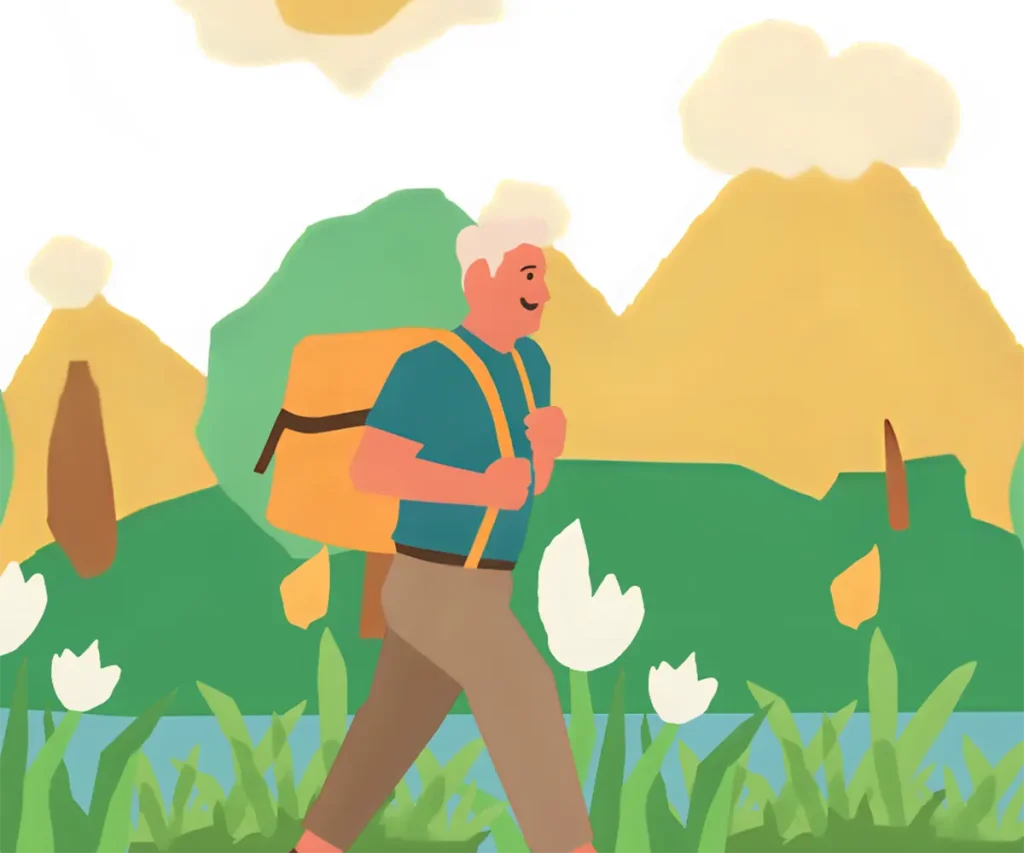

基本装備|必ず揃えておきたい登山の必需品
登山と聞くと、大きなリュックにぎっしりと道具を詰め込むイメージがあるかもしれませんね。けれども、標高300メートルほどの低山に挑戦する60代シニアの方にとって、本当に必要なのは「安心して歩けるための基本装備」なんです。ここで注目すべきは、山頂を目指すよりも安全に帰ってくること。つまり、無理なく快適に楽しめるための準備こそが大切なんです・・・!
低山登山でも必須の持ち物
一見すると軽いハイキングのように思えても、自然の中ではちょっとしたトラブルが起こりやすいものです。忘れてならないのは「少なくてもいいから安心できる装備」を持つことですよ。
- 飲み物(水筒やペットボトル):こまめな水分補給が欠かせません。
- 行動食(飴やナッツ):エネルギー切れを防いでくれます。
- 帽子・手袋:日差しや転倒の際のケガ防止に役立ちます。
- タオル:汗を拭くだけでなく、冷却や応急処置にも使えます。
- 簡易雨具:天気の変化は意外と早いので必ず準備を。
初心者が見落としがちな注意点
特に目を引くのは「持ち物の重さ」です。必要だからと詰め込みすぎると、足腰に負担がかかり、せっかくの楽しみが苦痛になりかねません。
| 装備品 | 注意点 |
|---|---|
| 水分 | 重くなりすぎないよう500ml程度から |
| 食べ物 | 消化のよいものを少量ずつ |
| 雨具 | 軽量タイプを選ぶと安心 |
| 帽子・手袋 | 季節に合わせて通気性や保温性を確認 |
つまり、軽さと安全性のバランスがカギになるんです。
ワンポイントアドバイス
装備を整えることは、自分自身を守ることにつながります。特筆すべきは、低山であっても「備えておいてよかった」と思う場面が必ずあるということ。だからこそ、最初の一歩からきちんと準備する習慣を身につけると安心です。
「全部を新品で揃える必要はありません。まずは手持ちの帽子やタオルなどから活用し、不足分だけを登山用品店で相談しながら揃えていくと無理なく始められますよ!」


足元を守る|シニアに適した登山靴と靴下の選び方
実は、登山で一番トラブルが起きやすいのは「足元」なんです。特に60代から始める方にとって、靴や靴下の選び方は体力以上に重要といえるでしょう。なぜなら、ちょっとした段差や滑りやすい道でも、足をしっかり支えてくれるかどうかで安心感がまったく違うからです。標高300メートル程度の低山でも、舗装されていない道は意外に歩きづらいもの・・・。初心者こそ「適切な靴と靴下」が欠かせないということなんです。
登山靴を選ぶポイント
登山靴といっても種類はさまざまです。低山の初心者におすすめなのは「ミドルカットの軽量タイプ」。足首を適度に守りつつ、歩きやすさも確保できます。
- 軽さ:重すぎる靴は疲労の原因になります。
- フィット感:かかとが浮かないものを選ぶと安心。
- 防水性:朝露や小雨でも快適に歩けます。
- ソールのグリップ力:滑りやすい土の道に効果的。
| 種類 | 特徴 | シニアにおすすめ度 |
|---|---|---|
| ローカット靴 | 軽くて普段履き感覚だが不安定 | △ |
| ミドルカット靴 | 足首を守りつつ歩きやすい | ◎ |
| ハイカット靴 | 安定性が高いが重くなりやすい | ○ |
登山靴は、必ず専門店で購入するようにしましょう。足に合わない登山靴は事故やトラブルの元になります。登山専用の靴下を履いた上でマッチするものが最適です。
靴下を選ぶポイント
忘れてならないのは、靴下の役割です。靴下はクッション性と通気性を両立させることで、足の疲れや靴ずれを防いでくれます。
- 厚み:クッション性があり、足をやさしく包む厚さが安心。
- 素材:ウールや速乾性のある化繊が最適。
- 丈の長さ:くるぶしより上まであると、靴の縁で擦れるのを防ぎます。
ここで注目すべきは「普段の靴下で代用しない」こと。普通の綿靴下では汗がこもりやすく、靴ずれの原因になりやすいんです。
ワンポイントアドバイス
登山靴は必ず「午後に試し履き」してみましょう。足が少しむくんだ状態でフィット感を確認すると、実際の登山に近い感覚で選べるんですよ!
こんな記事も読んでみてね!
荷物を快適に運ぶ|ザック(リュックサック)のポイント
登山で意外と大切なのが、ザック(リュックサック)の選び方です。たとえ標高300メートルほどの低山でも、飲み物や雨具、救急用品などを持ち歩くと、ずっしりと重く感じてしまうものです。驚くべきことに、ザックの背負い心地ひとつで「楽しい登山」か「疲れる登山」かが変わってしまうんですね!シニア世代は特に、自分に合ったザックを選ぶことが大切なんですよ!!
リュック選びで注意すべきポイント
📌 まずは基本的な選び方を押さえておきましょう。
- 容量は20〜25L程度
- 低山ならこのサイズで十分です。大きすぎると不要な荷物を詰め込みがちになります。
- 背中にフィットする設計
- 腰や肩に負担がかかりにくいモデルを選びましょう。
- 軽量で丈夫な素材
- 無理なく背負える重さが安心です。
- ウエストベルト・チェストベルト付き
- 歩行中の揺れを防ぎ、安定して背負えます。
シニアにおすすめのポイント
ここで注目すべきは、「体への負担を減らす工夫」です。年齢を重ねると肩や腰に疲れを感じやすくなるので、次の点を意識してみてください。
- 背中が蒸れにくいメッシュ構造
- 荷物を小分けにできるポケット
- 背負ったときに軽く感じる設計
リュックの選び方比較表
| 項目 | おすすめ仕様 | 注意点 |
|---|---|---|
| 容量 | 20〜25L | 大きすぎると荷物を詰めすぎる |
| 素材 | 軽量ナイロンなど | 安価すぎると破れやすい |
| ベルト | ウエスト・チェストあり | 無いと肩に負担が集中 |
| 背面 | 通気性メッシュ | 夏は蒸れて疲れやすい |
荷物の詰め方の工夫
📌 リュックの中身も快適さを左右します。
- 重い物は背中側に入れる
- よく使う物は上の方や外ポケットに
- 荷物は必要最低限に絞る
こうすることで、歩きやすさが大きく変わります。
ワンポイントアドバイス
ザックを試すときは、実際に3〜4kgほど重りを入れて背負ってみてください。空のままだと軽く感じても、荷物を入れた途端に「合わない」と気づくことが多いんです。つまり、購入前に体感することが、快適登山への近道なんですよ!
最初から高価なものを購入する必要はありませんが、できれば街中でもリュックサックとして使えるものであれば、いろいろ使いまわしできますよ!




天候対策|レインウェアと防寒具のチェック
登山で見逃せないのが「天候対策」です。実は意外なことに、標高300メートルほどの低山でも、天気の変化は思った以上に早いんです。朝は晴れていても、午後には小雨が降ったり、木陰ではひんやりした風に体温を奪われたりすることもあります。つまり、無理のない登山を楽しむためには「雨」と「寒さ」の両方に備えておくことが大切なんです。
レインウェアを選ぶポイント
忘れてならないのは、傘やビニールカッパでは十分に対応できないということ・・・。山では両手を空けて歩けること、そして動きやすいことが必須条件なんです。
- 上下セパレートタイプがおすすめ(ポンチョは風に弱い)
- 防水性と透湿性のある素材を選ぶ
- 軽量でコンパクトに収納可能なタイプが安心
| レインウェアの種類 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| ポンチョ | 軽くて着脱が楽 | 風にあおられやすい△ |
| ビニールカッパ | 安価で手軽 | 蒸れて動きにくい△ |
| セパレート上下 | 防水・透湿性に優れる | やや値段が高め◎ |
防寒具のチェック
興味深いことに、低山でも体感温度は天候で大きく変わります。特に60代以降は冷えで体力を奪われやすいので、防寒具は必ず用意しておきましょう。
- 薄手のフリースや軽量ダウンが便利
- 重ね着できるタイプを持参すると調整がしやすい
- 首や手首を守る小物(手袋・ネックウォーマー)も効果的
荷物に加えておきたい工夫
レインウェアと防寒具はザックの中でかさばりがち。そこで注目すべきは「パッキング方法」です。
- 小さく丸めて専用袋に収納する
- すぐ取り出せる位置に入れておく
- 濡れたものを分けられるようビニール袋も一緒に
ワンポイントアドバイス
登山には、「三種の神器」というのがあって、それは安全かつ快適に登山を楽しむために欠かせない「登山靴、ザック(バックパック)、レインウェア」の3つを指すんですね!
一見、レインウェアや防寒具は「使わなかったから持って行かなくてもいい」と考えがちですが、登山する時は、必須アイテムだと覚えておきましょう。たとえ使わなかったとしてもそれは安心という保険になりますからね!




体力をサポート|トレッキングポールの活用法
「トレッキングポール=高齢者が使うもの」ではないんです。実際、街中で使う「杖とトレッキングポール」は、別物です。
登山で使うトレッキングポールは、まるで第3、第4の足のように体を支えてくれるため、足腰の負担を減らしながら安全に歩くことができます。たとえ標高300メートルほどの低山でも、急な坂道や下り道ではその効果を実感できるはずです。
トレッキングポールの主な効果
- 膝や腰への負担を軽減
- 下り坂では膝に大きな負担がかかりますが、ポールを使うことで体重を分散できます。
- バランスをサポート
- 不安定な足場やぬかるんだ道でも、ポールがあると転倒防止につながります。
- 歩行リズムを整える
- ポールをつくことでテンポよく歩け、疲れを感じにくくなります。
つまり、無理のないペースで歩くための「味方」になってくれる道具なんです。
注意すべき使い方のポイント
ただし、持ち方や使い方を誤ると逆に疲れてしまうこともあります。ここで注目すべきは「高さ調整」と「使う場面」です。
- ポールの長さ
- 平地では肘が90度になる高さが目安。登りはやや短め、下りは少し長めに調整すると安心です。
- グリップの持ち方
- ストラップに手を通し、手首で支えるように使うと疲れにくくなります。
- 使うシーン
- 登りでは体を押し上げるサポートに、下りではブレーキのように膝を守る役割を果たします。
ここで忘れてならないのは、ただ「持っているだけ」では効果が薄いということです。実際に体重をポールに分散させてこそ、効果を発揮します。
トレッキングポール選びの比較
| 種類 | 特徴 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 伸縮式(折りたたみ可能) | コンパクトで持ち運びやすい | ◎ |
| 一体型 | 丈夫で安定感がある | ○ |
| カーボン製 | 軽量で疲れにくい | ◎ |
| アルミ製 | 耐久性が高く価格も手頃 | ○ |
軽量なカーボン製や伸縮式は、初めて使う方にとって取り回しがしやすいのでおすすめですよ。
ワンポイントアドバイス
トレッキングポールは、怪我の発生を大きく軽減してくれます。個人的には下山時にとても役立っています。緩やかな山では、使わないこともありますが、低山でも岩場があったり急登があるようなところは、携帯していると安心ですよ!
こんな記事も読んでみてね!
健康管理の必需品|薬・救急セットの準備
登山は自然を楽しむすばらしい時間ですが、60代から始める方にとって「健康管理」がいちばん大切なポイントになります。たとえ、標高300メートルほどの低山でも、ちょっとした体調不良や転倒が思わぬトラブルにつながることがあるんです。だからこそ、薬や救急セットの準備は欠かせない装備のひとつになるわけです。
登山で持っておきたい薬の種類
忘れてならないのは、自分の体に合わせた薬を持っていくことです。特に60代になると、日常的に服薬している方も多いですよね。
最低限、以下のような薬は準備しておくと安心です。
- 常用薬(血圧、心臓、糖尿病などの処方薬)
- 頭痛薬や鎮痛剤
- 胃腸薬
- かゆみ止めや抗アレルギー薬
- 風邪薬(初期症状用)
とりわけ注目すべきは「常用薬」。登山中に急に服薬できないと大きなリスクになります。忘れないように小さなケースに分けて持ち歩くと便利ですよ。
救急セットの基本アイテム
救急セットも意外とシンプルで十分だということです。低山であれば、重装備をする必要はありません。必要なのは「応急対応ができる最低限のもの」です。
- 絆創膏(大・小)
- ガーゼ、テーピング
- 消毒液や除菌シート
- 虫刺され用薬
- 三角巾(ケガの固定用)
これらをまとめてジップ袋に入れておくと、かさばらず清潔に持ち運べます。
持ち物チェック表
| カテゴリー | アイテム例 | ポイント |
|---|---|---|
| 薬 | 常用薬・頭痛薬・胃腸薬 | 常用薬は必ず日数分+予備 |
| けが対策 | 絆創膏・ガーゼ・テーピング | 小さな擦り傷にも対応 |
| 衛生管理 | 消毒液・除菌シート | 食事前の手拭きにも活躍 |
| 自然対策 | 虫よけ薬・かゆみ止め | 夏の低山では必須 |
ワンポイントアドバイス
薬や救急セットは、リュックのすぐ取り出せる場所に入れておきましょう。いざという時に奥底から探していると慌ててしまいます。つまり、「すぐ使える工夫」こそが安心につながりますからね!
普段から薬を必要としない生活をしている方も、登山用のファーストエイドキットというのがありますので、そういった救急セット一つ持っておくと震災や防災用に使えますよ!




道迷い防止|地図・コンパス・GPSの使い分け
低山だからといって油断してしまうと、意外にも道に迷う危険が潜んでいます。標高300メートル前後の里山でも、分岐が多く標識が少ない道では方向を失いやすいんです。実は道迷いの多くは「体力不足」よりも「判断ミス」から起こると言われています。だからこそ、地図やコンパス、GPSを上手に使い分けることが大切なんですね。
地図|全体像を把握する道具
紙の登山地図は、道の分岐や休憩ポイントを確認できる基本のアイテムです。
忘れてならないのは、地図を「リュックの奥」にしまい込まず、すぐ取り出せるようにしておくことです。
- ルートの全体像がわかる
- 万一スマホが使えなくても安心
- 登山口や下山口の確認ができる
コンパス|方向を確認する道具
地図とセットで使うことで威力を発揮します。特筆すべきは「進むべき方向を確実に示してくれること」です。
- 道が分かれた時に方角を確認できる
- 木々に囲まれた中でも方向感覚を失わない
- 紙地図と合わせれば「今どこにいるか」がわかる
正直、使えないならコンパスは持ってく必要がありません。
GPS(スマホアプリ)|現在地を知る道具
興味深いのは、近年はスマホの登山アプリがとても便利になっていることです。ただし重要なのは「過信しすぎない」こと。
- ワンタッチで現在地が表示される
- 登山道から外れるとアラートが出るアプリもある
- ただし電池切れや圏外のリスクがある
現代は、スマホ登山アプリが道案内の主流になっています。自分は、「ヤマレコ」を使っています。
使い分けのポイント表
| 道具 | 強み | 注意点 |
|---|---|---|
| 地図 | ルート全体を把握できる | 文字が細かく読みにくいことも |
| コンパス | 正しい方向を示す | 初心者では使えない |
| GPS | 現在地がすぐわかる | 電池切れ・圏外に弱い |
ワンポイントアドバイス
登山では、GPS付きのスマホアプリで登山道の確認をするのが一般的になっていますが、山でスマホを落としてしまうと、石に当たって壊れてしまう場合や、取れないところに落ちてしまう場合があります。このように「どれかひとつに頼ると危険」なので、紙の地図+スマホ登山アプリを基本するとよいでしょう。
またGPSを使っていると、電池の消費が激しいので余裕があればモバイルバッテリーを持っていくようにしましょう。




安全を守る|ヘッドランプや携帯電話のチェック
登山というと明るい日中の活動をイメージする方が多いですが、実際には思わぬ遅れや天候の変化で下山が夕方以降になることがあります。たとえ、標高300メートルほどの低山でも、林の中に入ると驚くほど暗くなるものです。そこで忘れてならないのが、ヘッドランプと携帯電話のチェックなんです。実はこの二つ、持っているだけで安心感がぐんと増しますよ!
ヘッドランプは必ず携帯しよう
低山だからと油断しがちですが、足元が見えにくくなると転倒の危険が増します。とりわけシニア世代はバランスを崩しやすいため、暗さへの備えは必須です。
- 軽量・LEDタイプがおすすめ
- 長時間点灯しても電池が持ちやすく、扱いやすいのが魅力です。
- 両手が自由になる安心感
- 懐中電灯と違い、手をふさがないので安全性が高まります。
- 電池残量を出発前に確認
- 「持ってきたのに電池切れ…」というのは意外とあるあるなんです。
ヘッドランプは何かあったときに必要になるものです。山の中で足を挫いて下山できなくなった場合でも、山はあっという間に暗くなりますので持っているだけで安心感が違います。
携帯電話は“命綱”になる
一方で興味深いのは、普段何気なく使っている携帯電話も山では心強い相棒になることです。連絡や情報収集だけでなく、ライトや地図アプリとしても使えます。
- 充電は満タンに
- 写真やアプリ使用で思った以上にバッテリーが減ることもあります。
- モバイルバッテリーを携帯
- 小型で軽いもので十分、予備があると安心です。
- 電波が届かない場所もある
- 事前に家族に行き先を伝えておくと不安が減ります。
低山でも必要なチェックポイント
| 項目 | チェック内容 |
|---|---|
| ヘッドランプ | 点灯確認・予備電池の有無 |
| 携帯電話 | フル充電・モバイルバッテリー持参 |
| 出発前の連絡 | 行き先と帰宅予定時刻を家族に伝える |
ここからわかるように、低山であっても「暗さ」と「通信トラブル」に備えることが、安全登山の大きなポイントになるんです。
ワンポイントアドバイス
ヘッドランプは、日帰り登山でも必ずザックに入れておきましょう。そして携帯電話は「通話ができればいい」ではなく、地図やライト代わりになる“多機能ツール”として意識することが安心につながりますよ!
こんな記事も読んでみてね!
命を守る水と行動食|少し多めに持参しよう
登山と聞くと「体力が一番大事」と思いがちですが、忘れてならないのは、水分と食料の確保こそ命を守る基本ということです。標高300メートルほどの低山でも、汗をかけば脱水症状を起こすことがありますし、エネルギー不足で足が重くなることもあります。つまり、安心して山歩きを楽しむには「少し多めに持つ」ことが鍵になるんです。
水分の目安と注意点
何よりも重要なのは水分補給です。低山だからと油断すると、あっという間に喉が渇いてしまいます。特にシニア世代は、喉の渇きを感じにくいこともありますので要注意です。
📌 持参量の目安(標高300m前後・日帰り登山の場合)
| 状況 | 水分量の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 涼しい季節 | 500ml〜1L | ペットボトル1本で足りる場合も |
| 暑い季節 | 1.5〜2L | スポーツドリンクを混ぜると◎ |
| 念のため | +500ml | トラブルに備えて余分に持参 |
- 500mlのペットボトルを2〜3本分持つと安心です
- 水筒に常温水、ペットボトルにスポーツドリンクなど分けるのも良いです
- 飲むときは一度にゴクゴクではなく、少しずつこまめに が基本です
行動食のポイント
「ちょっとお腹が空いたな…」と感じたときにすぐ口にできる食べ物が行動食です。登山中は思っている以上にエネルギーを消耗します。要するに、行動食はガソリンのようなものなんですね。
📌 おすすめは以下のような、軽くて食べやすいものです。
- ナッツ類(アーモンド・カシューナッツなど)
- ドライフルーツ(レーズン・マンゴーなど)
- エネルギーバー(カロリーメイトやプロテインバー)
- 小分けのチョコレートや飴
持参のコツ
- 取り出しやすいポケットに入れておく
- 個包装タイプを選ぶと衛生的で便利
- 塩分補給も考えて塩飴を加えると◎
ワンポイントアドバイス
実は、低山ハイキングでは「大丈夫だろう」と水や食料を少なく持って出発する方が多いんです。ところが、道迷いや休憩の増加で時間が長引き、最後にはフラフラ…というケースも・・・。
けれども、万が一のとき頼れるのは自分の荷物だけです。少し多めに持つくらいがちょうどいいんですよ!
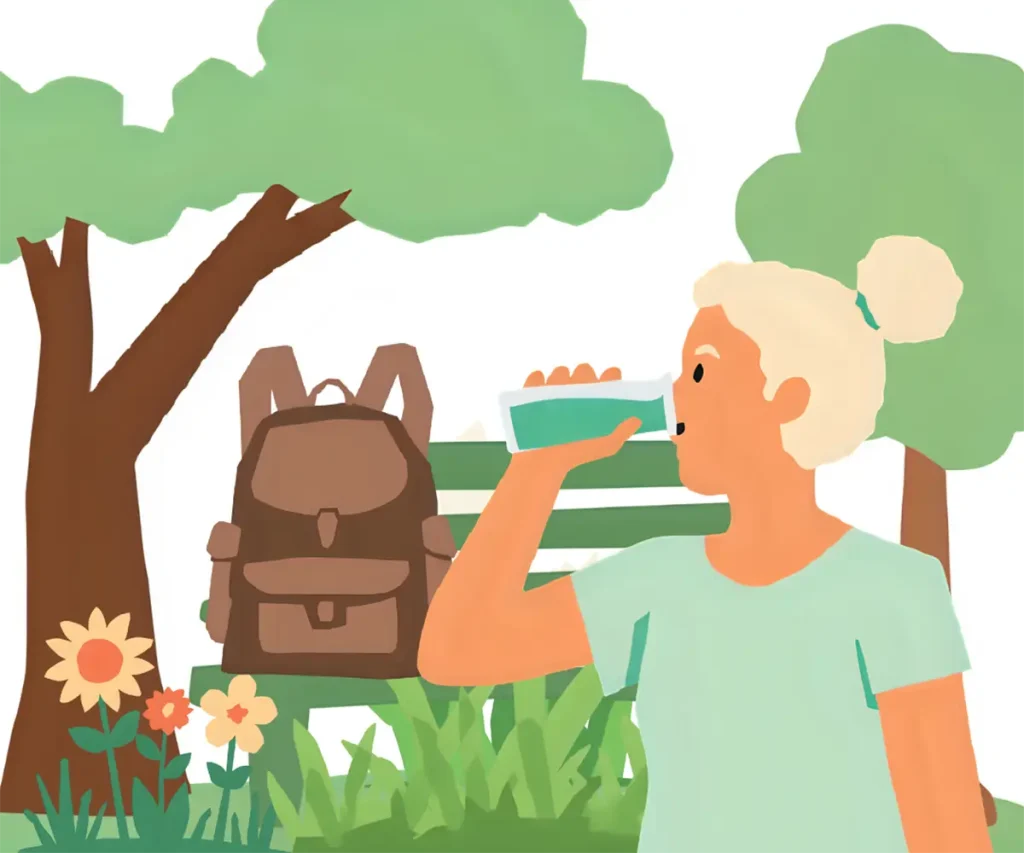
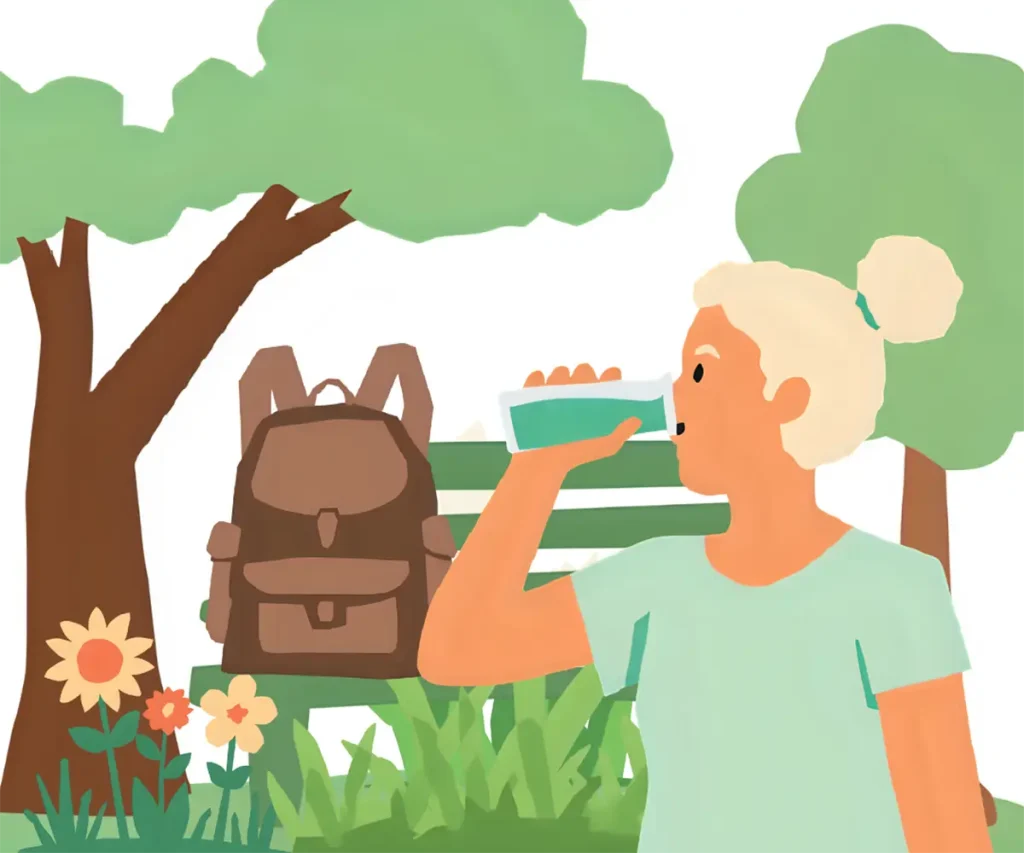


登山をもっと安心に|保険と緊急連絡体制を整える
登山を始めるとき、多くの方が装備や体力に目を向けがちですが、忘れてはならないのが「万一の備え」です。実は、標高300メートルほどの低山でもケガや体調不良は起こり得るんです。
まずは最低限の緊急連絡体制を整えておきましょう。
緊急連絡体制を整える
登山前には、家族や友人に「行き先・ルート・帰宅予定時間」を伝えておくことが何よりも重要です。実際、登山届を出さずに迷ってしまい、発見が遅れるケースは少なくありません。
📌 最低限、次のことを意識しましょう。
- 登山届をアプリやWebで提出
- 携帯電話のバッテリーを満充電
- 緊急時の連絡先(家族・地域警察)を紙でも控える
注意喚起としてお伝えしますが、低山だからといって油断しないことです。300m程度の山はハイカーも多い反面、分岐が複雑で迷いやすい場所もありますから・・・。だからこそ、事前の共有と緊急連絡先の確保が安心につながりますよね!
登山保険も視野に・・・
登山保険は「大げさでは?」と思う方もいますが、実は意外にも低山でも役立つシーンは多いです。たとえば転倒による骨折や、道迷いでの捜索などです。保険選びでは以下をチェックしてみましょう。
- ケガや入院の補償:通院費や入院費に対応しているか
- 捜索・救助費用:数十万円単位になることもあるので重要
- 日帰り対応か:低山ハイキングなら日帰りプランで十分
ワンポイントアドバイス
「今日は大丈夫だろう」と思った日に限って、思わぬことが起こるものです。何かあったときに対処しやすいように家族や友人へは必ず行動予定を伝えておきましょう。余裕のある方は登山保険を利用するのも一つの手です。安全と安心は最初の一歩から備えておきましょうね!




60代から始める登山の安全装備チェックリストで よくあるQ&A
還暦を迎えてからの登山は、ただの趣味ではなく「人生を豊かにする新しい挑戦」です。今回ご紹介した安全装備を整えれば、300メートル前後の低山でも安心して歩けますし、登頂の達成感を味わえるはずです。つまり、装備は不安を解消し、楽しさを倍増させるためのパートナーなんです。小さな一歩から始めてみるだけで、景色も人生も大きく変わっていくもの。大切なのは「無理をせず、楽しむこと」。今こそ、自然の中で心と体を解き放つチャンスです。あなたも安全装備を味方にして、新しい冒険を始めてみませんか?


















