「まさか自分が…」そんな言葉をよく耳にするのが、巧妙に仕組まれた“特殊詐欺”です。
特にシニア層は、家族を装った電話や役所からの通知に対し、真面目に応じてしまいがち・・・。だからこそ、まずは“どんな手口があるのか”を知ることが、最大の防御になります。
本記事では、シニアを狙う代表的な詐欺の手口や種類、そして未然に防ぐための具体的な対策まで、わかりやすく丁寧に解説。家族を守る一歩を、ここから始めましょうね!
シニアが狙われる“特殊詐欺”とは?|まずは把握から…
高齢者が被害に遭いやすいと言われる“特殊詐欺”・・・。
なぜシニア世代が狙われるのか、ちょっと不安になりますよね。でも大丈夫ですよ!まずは “特殊詐欺” の仕組みや特徴を知ることからはじめましょう。
特殊詐欺とは?
特殊詐欺とは、電話や手紙、SNSなどを通じて、お金やキャッシュカードをだまし取る犯罪です。
📌 警察庁では以下のように分類されています。
| 詐欺の種類 | 主な手口 |
|---|---|
| オレオレ詐欺 | 親族を装って「事故を起こした」「会社でトラブル」などと偽る |
| 還付金詐欺 | 役所職員を装って「お金が戻ります」とATMへ誘導 |
| 架空請求詐欺 | メールやハガキで「未払い料金があります」と不安をあおる |
| 金融商品詐欺 | 儲かる投資話を持ちかけて金銭をだまし取る |
| 融資保証金詐欺 | 「融資できます」と言って先に手数料を支払わせる |
| サポート詐欺 | 「ウイルス感染」などと偽ってリモート接続をさせる |
こうして見ると、いずれも “言葉”や“心理的な揺さぶり”が中心の詐欺 だとわかりますね。
だから、まずは正しい知識を持つことがなによりの防御策なんです。
なぜシニアが狙われやすいの?
📌 詐欺グループは、以下のような「狙いやすい特徴」を見抜いてきます。
- 固定電話を使っている
- 留守電設定をしていない
- 世間話にも丁寧に応じてしまう
- 金融機関や役所への信頼が高い
- パソコンやスマホに不慣れ
つまり、「親切な人ほどターゲットにされやすい」ということなんですね・・・。
だから、そんなやさしい人が詐欺に騙されないようにするためには、“ちょっとした備え”が必要なんです。
まず意識したい3つのポイント
では、どんな心構えが大切なのでしょうか?
📌 まずは以下の3つを意識してみてください。
- 知らない番号はすぐに出ない
- 少しでも不安を感じたら誰かに相談する
- 「急いで」「秘密に」は詐欺のサイン
実は、これだけでも被害を大きく減らすことができるんですよ!
こう考えると、まず「知っておく」ことがどれほど大切か、感じてきませんか?
“だまされない自分”は、正しい知識から育っていくものなんです。
ワンポイントアドバイス
特殊詐欺の被害者の約8割は高齢者、という事実をご存知でしたか?
ところが意外にも、手口を知っていても「自分はだまされない」と過信している方も多いんですよね・・・。だから何よりも重要なのは、詐欺師が常に新しい手口を生み出しているという現実を認識し、常に最新の情報をアップデートしていく姿勢だと思うんです。
まずはこのブログで様々な詐欺の手口をしっかりと頭に入れて、心の準備をしておきましょう。つまり、知識こそがあなたを守る一番の盾だということなんです!


オレオレ詐欺にご用心|身近な人になりすます手口とは
「おれだけど、事故を起こしてしまって…」
そんな一言から始まるのが、オレオレ詐欺です。
声が似ていないことも多いのに、なぜか信じてしまう──。その背景には、心理的な焦りと親心が潜んでいるんですね・・・!
オレオレ詐欺の典型的な手口とは?
詐欺グループは、電話で身内を名乗り、トラブルをでっち上げてお金をだまし取ろうとします。
📌 よくあるパターンはコチラ!
| 話の流れ | よく使われるセリフ |
|---|---|
| 1-身内を名乗る | 「オレだけど、声でわからない?」 |
| 2-トラブルを演出 | 「事故を起こした」「会社のお金を使ってしまった」 |
| 3-第三者を装って話を補強する | 弁護士・警察・上司になりすまし、「今すぐ必要」と急がせる |
| 4-お金を要求 | 「現金を取りに行かせる」「口座に振り込んでほしい」など |
こうして見ると、“不安”と“急がせ”がセットになっているのが特徴です。
つまり、「冷静な判断を奪うこと」が目的なんですね。
だまされないための“気づき”のコツ
では、どんな点に気をつけるとよいのでしょうか?
📌 以下のポイントを覚えておくと安心ですよ!
- 声が違うと感じたら、本人にかけ直す
- 「誰にも言わないで」は危険信号
- 「お金を取りに行く人」は詐欺グループの仲間
一見すると当たり前のように感じますが、不安になると判断力が鈍るのが人間なんです。
なので、一度電話を切って冷静になることがなにより大事なんですよ。
親心につけ込まれないために
オレオレ詐欺の本質は、「家族を守りたい」という気持ちを逆手に取ってくるところです。つまり、やさしさの裏をかく卑劣な詐欺だということです。
そんな卑劣な詐欺から身を守るため、「事前の家族ルール」がオススメです。
📌 たとえばこんな取り決め、してみませんか?
- トラブル時は必ず「合言葉」を使う
- お金の話は電話だけで済まさない
- 「知らない人に現金を渡さない」は家族の合言葉
つまり、小さなルールこそが大きな防波堤になるんです。
ワンポイントアドバイス
息子さんや孫を名乗って電話がかかってきたら、動揺してしまって当然ですよね。
でも、まさにそのときこそ、いったん電話を切って、本当に本人に連絡してみることが鍵になるんです。忘れてならないのは、犯人はあなたが慌てて冷静な判断ができなくなるように、切羽詰まった状況を装ってくるということです。
たとえ「電話番号が変わった」と言われても、すぐに信じずに、以前から知っている元の電話番号にかけ直す一手間を惜しまないでください。そんな時の有効手段として、家族言葉を決めておくことも、ちょっとしたポイントになりますよ・・・。


還付金詐欺の見抜き方|役所を名乗る電話に注意しよう
「医療費が戻ります」「保険料の払い戻しがありますよ」
そんな“おトクな電話”がかかってきたら、つい信じてしまいそうになりますよね。
でもちょっと待ってください。それ、“還付金詐欺”の可能性があるかもしれませんよ!
そもそも還付金詐欺ってなに?
還付金詐欺とは、税金や保険料の“還付”を装って、ATMへ誘導する詐欺の一種です。
主に市役所や区役所、年金機構、税務署などの“それらしい肩書き”を名乗るのが特徴です。
📌 以下は、よくある流れをまとめた表です。
| 詐欺の流れ | よくあるセリフ例 |
|---|---|
| 1,電話がかかってくる | 「こちら市役所です。保険料の還付手続きの件で…」 |
| 2,ATMへの誘導 | 「今日中なら、ATMで手続きできます」 |
| 3,操作させて送金させる | 「○○ボタンを押してください、それで完了します」 |
| 4,気づいたときには送金済み | 実は“引き出し”ではなく、“振り込み”させられていた |
こうして見ると、「手続きはATMでOK」と言われたら、疑ってみることがとても大事なんですよ!
騙されないための“気づきのポイント”
詐欺に引っかからないためには、「ちょっとした違和感」に気づくことがカギになります。
📌 以下のような場面では、立ち止まってみましょう。
- 役所がATM操作をお願いすることは絶対にありません
- 還付金の手続きが急すぎる(例:今日中に)
- 口座番号や暗証番号を聞いてくる
- 電話口で案内されながらATMへ行かせようとする
つまり、“急がせる・ATMで済む・非対面”の3点セットには注意が必要ということです。
知っておきたい!防止のためのヒント
では、実際にどうやって対策すればよいのでしょうか?
📌 今日から実践できる、カンタンな予防策をご紹介しますね。
- 留守電設定をONにする(詐欺電話はメッセージを残しません)
- 役所関係の電話は、折り返して確認する習慣をつける
- “還付金がATMで手続き可能”という話は一度も信じない
- 家族と「こんな電話あったよ」と共有するようにする
実はこれだけでも、還付金詐欺のほとんどは未然に防げると言われているんですよね!
ワンポイントアドバイス
耳障りのいい「払いすぎた税金や保険料が戻ってきます」という甘い誘いに、うっかり乗ってしまいがちですよね。でも、頭の隅においていただきたいのですが、役所や公的機関の職員が、還付金の手続きでATMの操作を指示したり、携帯電話を持ってATMに行くように促したりすることは絶対にないという点なんです。
だから「ATMへ行って」と言われたら、それは詐欺の決定的なサインだと見抜き、すぐに電話を切って、最寄りの警察や消費生活センターに相談してくださいね!
こんな記事も読んでみてね!
架空請求詐欺の対処法|慌てず冷静に対応するコツ
「身に覚えのない請求が届いた」「裁判になりますって書かれてて不安…」
そんな通知やメールを受け取ったら、ドキッとしますよね。
でも安心してください。その請求、本当に支払う必要はあるのでしょうか?
そうなんです!実はその“焦らせてくる請求”こそが、架空請求詐欺のサインだったりするんです。
架空請求ってどんなもの?
架空請求詐欺とは、実際には契約もしていないのに「料金未納」「裁判になる」といった脅し文句で金銭をだまし取る手口です。
特にシニア世代の方を狙って、はがきやメール、SMS(ショートメール)で突然届くことが多いんですよ。
📌 以下のような文面には、要注意です。
| よくある文言 | 注意すべきポイント |
|---|---|
| 「未納料金が発生しています」 | 実際には利用していないサービスが多い |
| 「民事訴訟を起こされます」 | 法的な手続きを匂わせて焦らせてくる |
| 「本日中に連絡してください」 | 急がせることで冷静な判断を奪おうとする |
| 「取り下げるには××へ連絡を」 | 偽の相談窓口に誘導される |
要するに、“不安をあおって、今すぐ連絡させようとする”のが、最大の特徴なんです。
騙されないための心がまえ
架空請求に対して一番大切なのは、「まずは深呼吸」です。
つまり、慌てず冷静に対処することが、最大の防御策になるんですよ!
📌 たとえば、こんな風に考えてみましょう。
- 「本当に支払いが必要なら、内容証明や正式な書面で届くはず」
- 「電話番号や送り元が不自然じゃないか確認してみよう」
- 「自分一人で判断せず、誰かに相談してみよう」
つまり、“今すぐに払わなきゃ”と思ったときこそ、立ち止まるサインなんですね。
実際の対処法|こんな行動があなたを守ります
📌 では、架空請求が届いたとき、どうすればいいのでしょう?
- 連絡をしない・無視する
- 相手に反応すると、さらに狙われやすくなります。
- 内容をメモして保存しておく
- はがき・メール・SMSなどは、証拠として保管しておきましょう。
- 家族や信頼できる人に相談する
- 客観的な目線で見てもらえるだけで、冷静になれますよ。
- 消費生活センターや警察に相談する
- 本当に困ったときは、188(消費者ホットライン)を活用しましょう!
こう考えると、架空請求ってそこまで怖くないなって思いませんか?
つまり、“慌てなければ、だまされることはない”んです。
むしろ、一呼吸おくことがあなた自身を守ってくれる鍵になりますよ!
だからこそ、「なんかおかしいな」と思ったらすぐ反応せず、まずは“無視して様子を見る”くらいでちょうどいいんです。
ちょっと勇気を出せば、冷静な自分に戻れるはずですからね。
ワンポイントアドバイス
身に覚えのない請求がメールやハガキで突然届くと、心もザワザワしちゃいますよね。でも犯人はあなたの不安をあおって、慌てて連絡してくるのを待っているんですよ・・・。
何よりも重要なのは、そこに書かれた連絡先に絶対に電話をかけたり、メールを返信したりしないことです。連絡すると、あなたの電話番号などの個人情報が相手に伝わってしまう危険があるんです
だから最善策は、無視することだったわけです。もし不安でたまらないときは、一人で抱え込まず、すぐに家族や警察に相談しましょうね!




金融商品詐欺の実態|うまい話には裏がある
「絶対にもうかりますよ」「今がチャンスです」…いきなりそう言われたら、ちょっと心が動いてしまうこと…ありますよね。
でも、うますぎる話には、たいてい裏があるものなんです・・・。
なぜなら、“簡単にもうかる話”ほど、詐欺師が好んで使うフレーズだからです。
金融商品詐欺ってどんな詐欺?
金融商品詐欺とは、株や未公開株、社債、暗号資産(仮想通貨)などを“かたちだけ”使って、実際には存在しない商品に投資させようとする詐欺のことです。
特に最近は、言葉が難しくて内容がわかりづらい「ハイテク投資」や「海外ファンド」などを装った詐欺が目立ってきています。
📌 以下のような言い回しには、要注意ですよ…
| よくある誘い文句 | なぜ怪しい? |
|---|---|
| 「元本保証で、毎月配当が出ます」 | 本来、投資に“保証”はありません! |
| 「あなたにだけ特別に案内しています」 | 他の人に言えない時点で、おかしいですよね |
| 「すでに多くの人が利益を出していますよ」 | 実際の実績は確認できないことが多いんです |
| 「今だけ限定。枠がすぐ埋まります!」 | 焦らせて、判断を鈍らせる手口なんです |
つまり、「急がせる・特別感を出す・確実に儲かる」がそろったら、まず疑ってみることが大事なんです。
騙されないために|ここをチェックしてみよう!
金融商品詐欺にだまされないためには、「え?本当かな?」と立ち止まる力が大切なんですね。
下のチェックポイントを活用して、冷静に見極めてみましょう。
📌 金融商品詐欺の見抜きポイント
- 商品内容がよくわからないのに勧めてくる
- 登録された金融業者かどうか、説明があいまい
- 契約書をきちんと読ませてくれない
- 話をせかされる、すぐにお金を振り込むよう言われる
- 「絶対に損しません」と強調される
ひとつでも当てはまったら、いったん持ち帰って誰かに相談してみましょう!
それだけで、大きな被害を防げることも多いんですよ。
相談すること=自分を守ること
実は、相談するって“慎重に生きる力”なんです。
迷ったら、金融庁や消費生活センター(188番)など、信頼できる窓口に遠慮なく相談してみましょう。
📌 ワンポイントアドバイス
- 「金融庁の登録業者かどうか」は、金融庁の公式サイトで確認できます!
- 電話で勧誘してきた場合は、「特定商取引法」で契約をクーリングオフできることもありますよ!
うまい話に飛びつきそうになったときこそ、一呼吸おいて「本当かな?」と立ち止まってみる。
実のところ、それが自分の財産と未来を守る、いちばんの近道だったりするんです。
ワンポイントアドバイス
「絶対に儲かる」「元本保証」「あなただけの特別な情報」といった、うまい話を耳にすると、心が揺らいでしまうこともあるかもしれませんね。しかし、そのような高利回りやリスクのない投資話は、ほぼ間違いなく詐欺だということです……。
まず最初にやらなければならないのは、取引をする業者が正規の登録を受けているかを、金融庁のウェブサイトなどで必ず確認するという冷静な対応が必要だということ・・・。
安易に現金を送ったり渡したりしないことが自分を守る鉄則なんですよ!
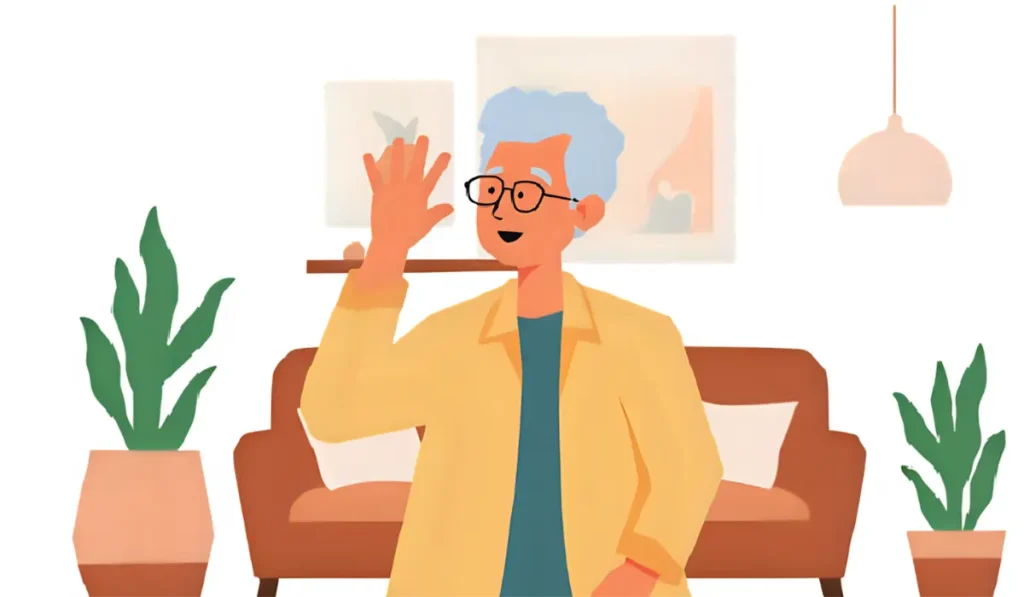
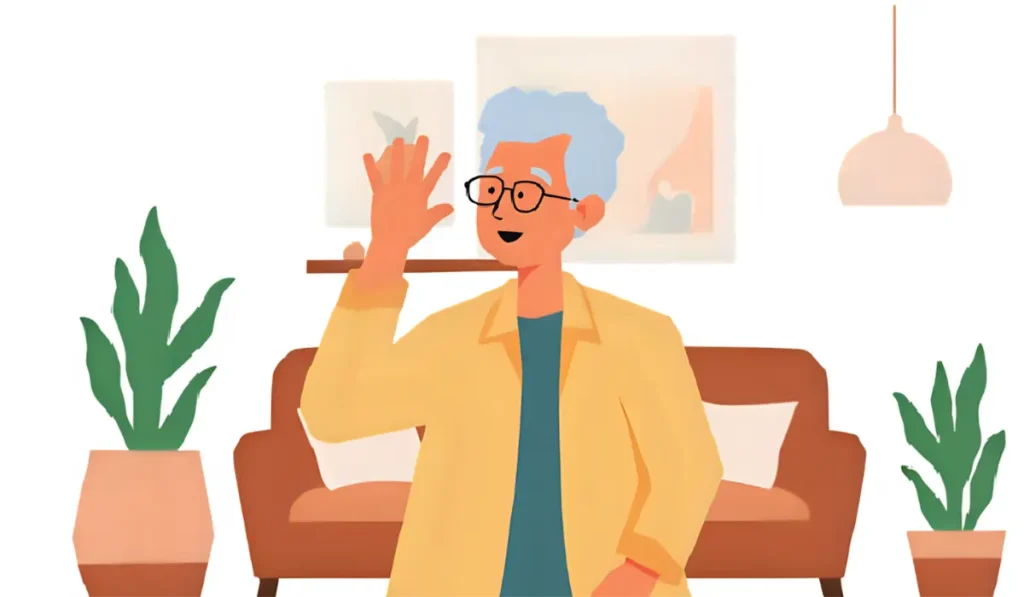


融資保証金詐欺とは|お金を借りる前に確認すべきこと
「今すぐ借りられますよ」「保証金を振り込んでいただければOKです!」
そんな言葉に、ちょっとホッとしてしまいそうになること…ありませんか?
でも、その“安心感”が、詐欺師にとってのチャンスなんです。
なぜなら、お金に困っている人の“焦り”や“期待”につけ込むのが、この融資保証金詐欺の手口だからです。
そもそも融資保証金詐欺って?
融資保証金詐欺とは、「お金を貸す」と言いながら、実際には融資をせず、保証金や手数料などの名目でお金だけをだまし取る詐欺のことなんです。
📌 被害にあいやすい場面は、こんなときかもしれません。
- 銀行の審査に通らなかったあと
- ネット検索で「即日融資」と書かれた広告を見たとき
- 携帯に届いたSMSに「融資可能」と書いてあったとき
- 実際に使われる誘い文句には、次のようなものがあります。
📌 実際に使われる誘い文句には、次のようなものがあります。
| よくある言い回し | 実はこんな落とし穴が… |
|---|---|
| 「どなたでも即日で借りられます」 | 審査がない時点で、まず怪しいです! |
| 「前金として保証金が必要です」 | お金を借りる前に払うのは、おかしいですよね? |
| 「振り込めば、すぐに入金されますよ」 | 入金されることは、ほぼありません… |
| 「他社で断られても、うちは大丈夫です」 | 弱みに付け込んでいる可能性大なんです |
つまり、“誰でも借りられる”ように見えて、実は最初から騙すつもりで近づいてくるわけです。
だまされないためのコツ|まずは「冷静にチェック」
実は、ちょっと立ち止まって確認するだけで、防げることって多いんですよ。
以下のようなチェックポイントを持っておくだけで、ぐっと安心感が増します。
📌 融資保証金詐欺のチェックポイント
- 登録された正規の金融機関かどうかを調べる(金融庁のサイトで確認できます)
- 「保証金」や「手数料」の前払いを要求されたら要注意
- 本当に会社が存在するか、所在地や電話番号をチェック
- 連絡手段がメールやLINEのみの場合は特に注意
- 審査なしで貸してくれるという話には、まず疑いを持つこと
お金を借りるときほど、“慎重”があなたを守るカギ
実は、融資が本当に必要なときって、少し焦ってしまいがち・・・。
でもそんなときこそ、「これは本物の業者かな?」とひと呼吸おいて確認するだけで、大きな被害を防げる可能性があるんです。
さらに、「相手からの連絡がしつこい」「すぐに振り込むように催促される」ときも、その時点でストップする勇気が大切なんです。
もし「ちょっとでも不安だな」と感じたら、消費生活センター(188)や金融庁の相談窓口にすぐ連絡してみましょう。
相談するのは、決して恥ずかしいことではありません。
むしろそれが、自分と家族を守るための一歩になるんですよ!
つまり、「借りる前に調べる」ことこそが、未来の安心をつくる行動なんです。
ちょっとした違和感に気づけたあなたなら、きっと、だまされることはありません!
ワンポイントアドバイス
「審査なしで即融資」「低金利で高額融資可能」というダイレクトメールやFAXを見ると、つい期待してしまう気持ち、わかります。しかし、融資を実際に行う前に「保証金」「手数料」などの名目で金銭を要求してくる業者は、ほとんどが詐欺だという点なんです。
言うまでもなく、正規の金融機関が融資前に保証金を振り込ませることはありません。そこで考えるべきは、融資を受ける前に金銭の振り込みを求められたら、それは危険なサインだと見逃さずに、その業者の登録の有無を公的な情報で確認することですよ!




サポート詐欺に騙されない|画面に突然現れる警告の正体
パソコンやスマートフォンを使っていたら、突然画面に「ウイルス感染!」「至急ご連絡ください!」といった警告が表示されたこと、ありませんか?
「えっ、どうしよう…」「何か押しちゃったのかな…」と、不安になってしまう方も多いはずです。
でも、それ、もしかしたら“サポート詐欺”かもしれません。
実はこの詐欺、ネットをよく使う人ほど遭遇しやすい新手の手口なんですよ。
サポート詐欺って、どんなもの?
サポート詐欺とは、「ウイルスに感染しました」「サポートセンターに今すぐ電話してください」と偽の警告を表示し、利用者に不安を抱かせて金銭をだまし取る詐欺のことです。
📌 よくある流れはこんな感じです。
| 手口の流れ | 実際に何が行われているか |
|---|---|
| 突然、警告画面が表示される | 偽のポップアップや広告です |
| 音声やアラートで「すぐに連絡を」と迫られる | 焦らせて冷静な判断力を奪おうとしています |
| 電話をかけると「遠隔操作します」と言われる | 相手にパソコンを乗っ取られてしまう危険があります |
| 修復費用やセキュリティ代を請求される | 数万円~数十万円をだまし取るのが目的です |
つまり、「あなたの不安」を利用して、冷静さを奪い、言いなりにさせようとする手口なんですね。
騙されないために|すぐにできる3つの対処法
実際に被害にあう人も増えているからこそ、知っておくと安心な“3つの対処法”を紹介します。
📌 サポート詐欺を防ぐためのアドバイス
- 警告が出ても、まずは慌てない
- 本物のウイルスなら、セキュリティソフトが静かに対応してくれます。
- 連絡先が「フリーダイヤル」や「海外番号」なら要注意
- 正規企業のサポートは、サイトから確認できます。
- 遠隔操作を求められたら、即断る
- パソコンを乗っ取られる危険があるので、画面を閉じてリセットしましょう。
加えて、ブラウザのポップアップをブロックしたり、広告ブロック機能を活用するのもおすすめです!
大丈夫。画面が怖くても、落ち着いて対処できます
実のところ、サポート詐欺に遭ってしまう人の多くは、「親切に見えたから」「信じたくなったから」なんです。
だからこそ、だまされたこと自体が恥ずかしいわけではありません。
むしろ、ちょっと立ち止まって冷静になれるあなたは、もうその時点で“被害を防げる人”なんですよ!
📌 「もしかして詐欺かも?」と思ったら…
- 画面をすぐ閉じる
- 通話はしない
- 信頼できる人や消費生活センター(188)に相談する
たったこれだけで、大きな被害を防げる可能性が高まるんです。
ちょっと前に自分のパソコンに出てきた詐欺画面(音は入っていません)
突然大音量の警告音とともに現れたこの画面。何を押しても消えず、しきりにWindowsサポートに電話するように促してきます。
もしもこのような画面が突然現れたら・・・・・
- 「Ctrl」 + 「Shift」 + 「Esc」を同時に押しタスクマネージャーを立ち上げる
- タスクマネージャーが起動したら、不審なアプリやプログラムが起動していないか確認する
- 不審なアプリが起動していたら、選択して「タスクを終了」をクリックする
- Google ChromeやMicrosoft Edgeのブラウザを終了する
ワンポイントアドバイス
パソコンやスマホの画面に突然「ウイルスに感染しました!」「すぐにここに電話してください!」と大きな音と共に警告が表示されると、びっくりして慌ててしまうのも無理はありません。しかし、その警告は偽物、つまり詐欺師があなたをだまそうと表示させたフェイク画面なんです。驚くべきことに、画面の電話番号にかけると高額なサポート料を請求されたり、遠隔操作で個人情報を盗まれたりします。したがって、画面に表示された電話番号には絶対にかけず、まずはブラウザを強制終了するか、電源を切って冷静になることが重要ですよ!
こんな記事も読んでみてね!
特殊詐欺を防ぐ家族の連携|一人で抱え込まない仕組みづくり
詐欺の被害に遭った人の多くが、「誰にも相談できなかった」と話します。
つまり、孤独が“詐欺の入り口”になってしまうことが多いんです。
ここで大事になるのが、“家族のつながり”による防止策。
少しの声かけや見守りだけでも、被害を防げるきっかけになりますから・・・。
家族で防ぐって、どういうこと?
特殊詐欺は、本人だけでは気づきにくい手口も多く、「まさか自分が…」と思ってしまうもの・・・。でも、家族や身近な人が一緒に関わっていれば、“気づく力”が何倍にもなるんです!
| 家族の関わりで変わること | 家族の関わりで変わること 実際の効果 |
|---|---|
| 電話や会話の変化に気づける | 詐欺師からの接触にいち早く気づける |
| お金の動きを一緒に見守る | 不審な送金や振込を防ぎやすくなる |
| 情報共有の機会が増える | 最新の詐欺手口を知るチャンスが広がる |
そう考えると、家族とのちょっとした関係づくりが、防犯の第一歩になるわけです。
実はカンタン!家族でできる見守り習慣
「でも、毎日一緒にいられないし…」
「忙しくて、つい後回しに…」という方も、大丈夫!
実は、ちょっとした習慣だけで安心感はぐっと変わるんです。
📌 家族でできる!詐欺防止のための3つのヒント
- 「困ったときは電話してね」と伝えておく
- あらかじめ相談しやすい関係をつくっておくことが大切なんです。
- 月1回は“お金の話”をしてみる
- 「最近誰かから電話こなかった?」など自然な会話から始めましょう。
- 詐欺のニュースを一緒にチェック
- 「これ、怖いね~」と話すだけでも、防犯意識が高まるんです!
こうして見ると、“日常の中のちょっとした会話”が、実は最大の防犯対策だったりするんですよね。
親しさが、防御力になる
大切なのは、「困ったときに、頼れる人がいる」と感じてもらうこと。
特に高齢の方は、「迷惑をかけたくない」という思いから、あえて相談を控えてしまうこともあるんです・・・。
📌 だからこそ、
- 「何かあったら、すぐ言ってね」
- 「一緒に考えるから、大丈夫だよ」
そんなひと言が、心の支えとなり、防犯の力になるんです。
ワンポイントアドバイス
結局のところ、防犯って「何かを疑う」ことではなく、「大事な人を信じること」なんだと思うんです。「何かあったら、ちゃんと話してくれる」そんな信頼関係ができていれば、詐欺師のつけ入るスキはありません。
つまり、一人で抱え込まなくていい仕組みを、家族の中に自然に作っておくこと。
それこそが、いちばんの詐欺対策なんですよ!




被害を未然に防ぐ行動とは|知識と準備で「だまされない自分」に
特殊詐欺は、「気づいたときにはもう遅かった…」というケースがとても多いんですね!
でも逆に言えば、少しの「準備」と「知識」で、防げる可能性がぐっと高まるということ。
そうなんです!
つまり、“だまされない自分”をつくるのは、日々のちょっとした習慣だったりするんですよ。
日常の中に「防犯スイッチ」を
防犯というと、特別な訓練が必要に感じるかもしれませんが、実際は、“少し立ち止まるクセ”があるかどうかが大きな分かれ道・・・。
| よくある詐欺の入り口 | 実はこんな対処で防げます |
|---|---|
| 急な電話や「至急振り込んで」と言われた | いったん切って、家族に相談する |
| 本物そっくりの封筒や通知 | 差出人や番号を検索して確認してみる |
| 「今だけ」「限定」など焦らせる文言 | その場で決めず、必ず一晩おいて考える |
つまり、“ちょっと待つ”“一人で決めない”ことが、被害を防ぐ鍵になるわけです。
だまされにくくなる3つのポイント
知らないうちに、「自分だけは大丈夫」と思っていませんか?
実は、油断しやすい人ほど、狙われやすいとも言えるんです。
📌 次の3つを意識してみてくださいね!
💡 1,「情報を知っておく」だけで違う!
- 詐欺の手口は、年々アップデートされています。
- 例えば、「マイナンバー詐欺」や「生成AIを使った声のなりすまし」など、新手の詐欺も登場中!
地域の防犯ニュースや市町村の広報などをチェックするだけでも安心につながります。
💡 2,「決断する前に、ワンクッション」
- 急がされる場面こそ、いったん深呼吸。
- 「後で折り返します」と言うクセをつけておくだけで、冷静さが戻るんです。
つまり、“考える時間”こそが最大の防犯策なんですね・・・。
💡 3,「防犯グッズ」もひとつの味方
- 留守番電話を設定しておくだけでも、詐欺電話は激減します。
- スマホに“詐欺対策アプリ”を入れておくのも効果的。
実はこうした小さなツール、あなたの味方になってくれるんです!
一番の対策は、“自分を信じること”
「こんな自分がだまされるなんて…」と自分を責める方が多いのですが、
詐欺師はプロ。誰にでも、どんな場面でも近づいてくるものなんです。
- ちょっとした違和感を信じてみること
- 「もしものときは誰かに相談していい」と思える自分でいること
それが、本当の“だまされない自分”を育てることにつながるんですね。
「今からできる」から、大丈夫!
被害を未然に防ぐために、完璧である必要はありません。
だから、まずはできることから、ひとつずつで大丈夫なんですよ!
- 1日に1回、防犯に関するニュースを見る
- 「すぐ決めない」を習慣にしてみる
- 留守電設定を試してみる
これらは、どれも今すぐできる対策ばかり・・・。
つまり、“だまされない自分”は、今日から育てられるということなんです。
ワンポイントアドバイス
「自分は大丈夫」という楽観性バイアスこそが、実は詐欺の最大の落とし穴だったりするんです。被害を未然に防ぐためには、日頃からの準備と知識のアップデートが不可欠だということ。
つまり、留守番電話機能を常にONにして、知らない番号からの電話には出ないという習慣をつけること。それと同時に、不審な電話の内容は、すぐに警察の相談専用ダイヤル(#9110)へ相談するという行動こそが、だまされない自分を作る鍵になるんですよ!
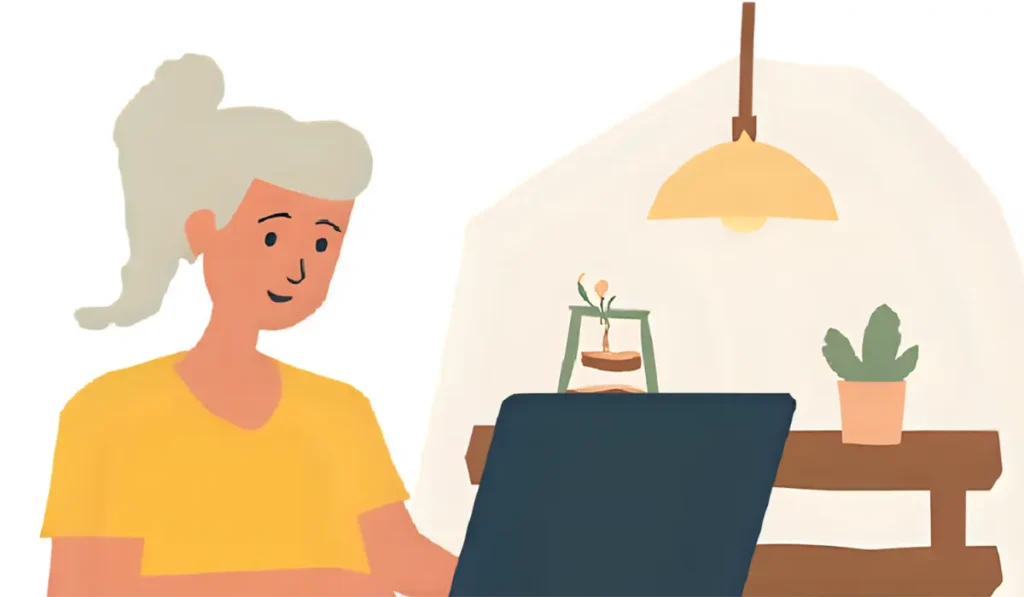
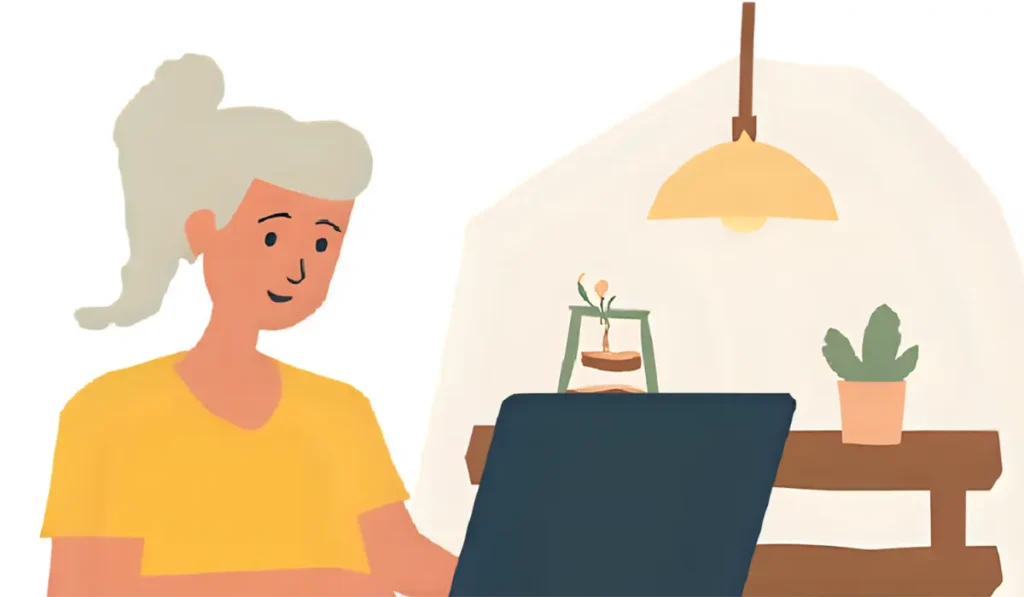


シニアが狙われる“特殊詐欺”とは?で よくあるQ&A
詐欺師は、あなたの「信じる心」や「不安な気持ち」に巧みに入り込んできます。オレオレ詐欺や還付金詐欺、架空請求に金融商品詐欺まで──その手口は年々進化し、誰もが被害者になりうる時代です。
しかし、恐れる必要はありません。大切なのは「知ること」と「備えること」。詐欺のパターンや兆候を知っておけば、冷静に判断する力が養われます。そして何より、一人で悩まず、家族と連携しておくことが最大の防御策です。「ちょっと変だな?」と思った時にすぐ相談できる環境こそ、詐欺を未然に防ぐ鍵になります。
だまされない力は、誰にでも育てられます。この記事を通じて、その一歩を踏み出してみてください。

















