「終活」と聞くと、少し重く感じるかもしれません・・・。
しかし実際には、60代から前向きに人生を整える大切なチャンスとも言えます。年を重ねていくための心の整理、家族への想い、これからの暮らしを豊かにするための準備が「終活」なのです…。
本記事では、「終活とは何か?」から始まり、身辺整理、エンディングノート、遺言、相続、介護まで、必要な知識をやさしく解説。後悔のない未来のために、今できることを一緒に考えてみましょうね!
終活とは?|60代で始める意味とメリット
年齢を重ねるにつれ、「終活」と聞くと、なんとなく他人事ではないような気がするこの頃……。
“終活”とは「人生の終わりに向けて、自分の暮らしや想いを整理すること」を意味しますが、怖いことでも、急ぐことでもありません・・・。むしろ、今の60代だからこそ、じっくり取り組める「前向きな準備」と言えるんです!
終活の目的とは?
終活の目的は、「自分らしく生ききること」と「家族に迷惑をかけずに旅立つ準備をすること」。
つまり、終活は“人生の最終章”を自分でデザインすることではないでしょうか!
📌 終活の主な内容は、以下のような項目です。
- 身の回りの整理(生前整理・断捨離)
- 財産の確認と相続対策(遺言・生前贈与)
- 介護や医療の希望(リビングウィル・延命措置の意思表示)
- 葬儀やお墓の希望(費用やスタイル)
- デジタル遺品(SNS・スマホデータ)の管理
- 家族へ伝えたい想い(エンディングノートなど)
60代で始めるメリットは?
📌 ここで注目すべきは、「終活は60代からがちょうどいい」という点です。
| 年代 | 特徴 | 終活との相性 |
|---|---|---|
| 50代 | まだ現役で忙しい時期 | 忙しくて後回しになりがち |
| 60代 | 健康に不安は少なく、時間にゆとりがある | 自分で決めて進められるベストタイミング |
| 70代以降 | 体力や記憶に不安が出てくる | 内容を整理するのが大変になることも |
つまり、60代は終活を“主体的に進められる”最後のゴールデンタイムともいえるんです。
終活を始めると、こんな変化が起こります
- 気になっていた物が片付き、心がスッキリする
- 将来の不安が減り、毎日の生活が前向きになる
- 家族との会話が増えて、つながりが深まる
つまり、終活は「終わりのための準備」ではなく、「これからを心地よく生きるための見直し」なんです。
ワンポイントアドバイス
終活と聞くと「終わり」を連想しがちですが、実は残りの人生を自分らしく「より良く生きるための準備」とも言えますよね! でも、終活をする本当の意味って、終活を通じて自分の価値観や本当に大切にしたいことを見つめ直せるとい点かもしれません・・・。
漠然とした不安を解消し、「これから」を主体的にデザインするための作業と捉えれば、心のハリが生まれるはず・・・。まずは「終活を始める理由」を紙に書き出してみましょう。そうすると、きっと終活がネガティブなものではなく、「未来への希望」になるはずですから・・・。


身辺整理と断捨離|心が軽くなる生前整理の始め方
「身辺整理」と聞くと、少し身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれません・・・。
でも、生前整理は“自分のため”でもあるんですね!
なぜなら、不要なモノや情報を手放すことで、気持ちまで軽くなりますから……。
生前整理とは?断捨離との違い
📌 そもそも「生前整理」と「断捨離」は同じように見えて、少しだけ目的が違います。
| 用語 | 意味 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 断捨離 | モノを減らして快適な暮らしにする考え方 | 日々の暮らしの見直し |
| 生前整理 | 財産や持ち物を整理し、遺される人の負担を減らす行動 | 終活の一環としての準備 |
そう考えると、まずは断捨離で暮らしを整えながら、生前整理につなげていく流れが自然なんですよ。
何から始めればいいの?
📌 どこから手をつけていいかわからない方へ…
- ステップ1:身近な場所からスタート
- 引き出しや棚など、小さなスペースから
- 古い書類、使わない家電、読み終えた雑誌などから手放す
- ステップ2:思い出の品は“選ぶ”ことから
- 写真や手紙は、残したいものを選別
- デジタル化しておくと、かさばらず安心です
- ステップ3:大きな物・資産は家族と共有
- 不要な家具の処分や寄付
- 預貯金や保険、相続に関する情報をノートにまとめる
実は、こんなメリットもあるんです
📌 生前整理を始めた人の多くが、次のような声を挙げています。
- 「部屋が片付いたら、心までスッキリした」
- 「家族と会話が増えて、未来の話もできるようになった」
- 「自分が元気なうちに決めておけて、安心できた」
モノを減らすことが、心のゆとりにもつながっていくということなんです。
無理せず続けるコツは?
忘れてならないのは、“がんばりすぎない”こと。60代からの終活は、少しずつ積み重ねていくものだからです…。
- 毎日15分だけ「整理タイム」を決める
- 終わったら、自分をねぎらうひとことを
- アプリやチェックリストを使って管理してもOK
こうして見ると、身辺整理も決して難しくないと思えてきませんか?
ワンポイントアドバイス
身辺整理や断捨離を始める際、「完璧にやろう」と意気込むと、途中で挫折しがちです・・・。
始めるポイントとしては、「思い出の品」から手をつけないことなんです。まずは、使っていない食器や洋服、古い書類など、「なくても生活に支障のないモノ」から少しずつ手放していきましょう
まだ動ける今のうちに、少しずつ始めてみて、無理のないペースで、暮らしと心の両方を軽くする・・・。それが、生前整理の本当の意味なんだと思います。


エンディングノートの活用|家族と自分をつなぐ記録
エンディングノートなんて、特別な人が作るものと思いがち・・・。でも実は、自分の「これから」と「大切な人たち」のために使える、やさしい未来ノートになるんです!
つまり、書いておくことで“もしものとき”に家族が困らず、日々の生活でも安心感が生まれる…。
そんな、あなたの思いを橋渡しする役割があるんです。
エンディングノートと遺言書の違いって?
📌 そもそも、「エンディングノート」と「遺言書」はどう違うのでしょうか?
| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |
|---|---|---|
| 法的効力 | なし | あり(法的書式が必要) |
| 書き方の自由度 | 高い(手書き・自由形式) | 形式に従う必要あり |
| 内容 | 思いや希望、連絡先、医療・介護の希望など | 財産分与・法的な相続の内容など |
| 家族へのメッセージ | 書ける | 書く人もいるが主目的ではない |
つまり、エンディングノートは“心の整理”のための記録とも言えるんですね。
何を書けばいいの?おすすめ項目一覧
📌 こんな書き方もありますよ…
- 基本情報と連絡先
- 本人のプロフィール(住所・生年月日・血液型など)
- 家族や親戚、友人の連絡先
- 医療機関・かかりつけ医・保険の情報
- 医療・介護についての希望
- 延命治療を希望するかどうか
- 自宅療養・施設入所などの希望
- 介護をお願いしたい人の名前
- 財産・契約に関するメモ
- 銀行口座や保険、年金の情報
- ネット銀行やサブスクなどの“デジタル遺品”リスト
- 遺言書がある場合はその保管場所
- 葬儀やお墓についての希望
- 葬儀の規模や方法(家族葬・音楽葬など)
- お墓の有無・場所・希望する供養の形
- 家族や大切な人へのメッセージ
- 「ありがとう」や「ごめんね」の気持ち
- 伝えきれなかった思い出話や未来への言葉
こうしてみると、一気に書こうとせず、少しずつ書き足していくのがコツなんですよ。
エンディングノートを書くことで得られるもの
📌 実際に書いてみた方たちからは、こんな声が寄せられています。
- 「家族との話し合いのきっかけになった」
- 「自分の考えを整理できて、不安が減った」
- 「まだ元気なうちに、準備できてよかった」
そうなんです!
書くことで“今の自分”と“これから”をつなぐ手助けになるわけです。
無理なく続ける3つのヒント
📌 書くことが目的ではなく、自分のためのツールとして気楽に使うことが大切です。
- 市販のテンプレートやアプリを使ってもOK
- 「今日はここだけ」と、1日1テーマにしてみる
- 書けたところまでで満足してもいいんです
ワンポイントアドバイス
エンディングノートを書く際、つい形式ばった項目から埋めようとしがちですが、何よりも重要なのは「想いを伝えること」です。まずは「自分の人生で楽しかったこと」や「家族への感謝のメッセージ」といった、気持ちが伝わる部分から書いてみてはどうでしょうか!
言い換えれば、これは単なる記録ではなく、家族の絆を深めるためのラブレターにもなるんです。だから、完璧でなくていいんですよ。少しずつ、あなたの言葉で埋めていくことが、残されたご家族にとってかけがえのない宝物になるはずです。
こんな記事も読んでみてね!
遺言と相続|円満な未来をつくる法的準備
誰にでも、いつかは訪れる“その時”・・・。その前に、家族の安心をそっと整えておく方法があるとしたら、どう感じますか?
実は、遺言や相続の準備こそが、家族への思いやりを形にできる大切な手段なんです。
「揉めないように…」「迷惑をかけたくない…」そう考えたときが、始めどきかもしれませんね。
遺言と相続の基本|知っておくだけで違います
「遺言=お金持ちのもの」と思われがちですが、実際はそうではありません。ごく普通の暮らしの中でも、“想い”や“もの”をどう引き継ぐかはとても大切なことです。
📌 以下の表で、基本的な違いを整理してみましょう。
| 項目 | 遺言(ゆいごん) | 相続(そうぞく) |
|---|---|---|
| 主な内容 | 誰に何を残すかを指定 | 故人の財産を家族が受け継ぐこと |
| 必要性 | 残したい意思があるとき | 遺言の有無にかかわらず発生する |
| 法的効力 あり | (公正証書・自筆など条件あり) | 民法に基づいて実施される |
| トラブル防止効果 | 高い | 遺言がないと、争いの原因になることも |
こうして見ると、遺言は“家族を守るための準備”とも言えるんですよ。
遺言を書くときに役立つポイント
📌 コツを知っていればスムーズに始められます。
- 形式は「公正証書遺言」がおすすめ
- 公証役場で作成し、法的に安心。紛失や無効の心配も少ないんです。
- 書く内容は“思い”と“分け方”をバランスよく
- 財産の配分だけでなく、感謝や気持ちも添えておくと家族に伝わりやすくなります。
- 元気なうちに作成して、定期的に見直す
- 状況は変わるもの。人生に合わせて更新していけるのが理想です。
つまり、完璧でなくてもいいんです。
「いまの自分の気持ち」を書き残しておくことが何より大切なんですよ。
相続の備え|早めの話し合いがカギ
実のところ、「うちは大丈夫」と思っていた家庭ほど、あとで揉めてしまうことも…。
だからこそ、相続について“事前に話しておく”ことが一番の対策なんです。
📌 話すときのコツは以下の通りです
- 財産の一覧を作っておく(預金・不動産・借入・保険など)
- 誰に何を渡すか、本人の意向を共有しておく
- 家族会議のような雰囲気で、気軽に話し合う
- 専門家(司法書士や行政書士)に相談するのも◎
つまり、話し合うこと自体が「相続対策」になるわけです。
無理なくできる3つのステップ
📌 こんな順番で進めてみると意外とラクなんです…
- エンディングノートに「遺言の希望」だけでも書いておく
- 自分の財産や気持ちを整理するために、簡単なリストを作ってみる
- 不安があれば、地元の専門家に無料相談をしてみる
そう考えると、遺言や相続ってそんなに怖くないですよね。未来の自分と家族が安心できる準備、一緒に始めてみませんか?
ワンポイントアドバイス
遺言と聞くと、なんだか「大変そう」「まだ早い」と感じてしまうかもしれませんね。しかし、遺言がないために、大切なご家族が話し合いで揉めてしまうケースは少なくなんです。
そこで浮かび上がるのは、「公正証書遺言」という選択肢です。これは、公証役場で作成するため、法的な有効性が非常に高く、手続きの明確さが円満な相続への最も確実な道なんです。
だから、「愛する家族のために、安心の土台を築く」という前向きな気持ちで、一度専門家に相談してみてはどうでしょうか!
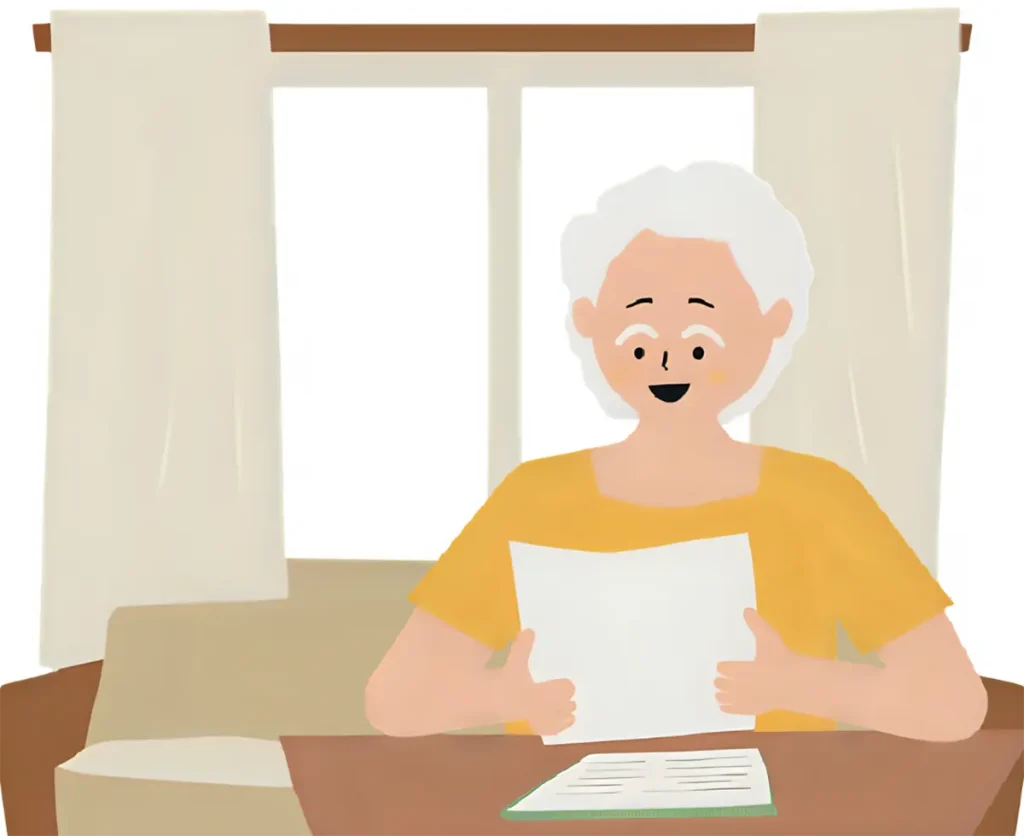
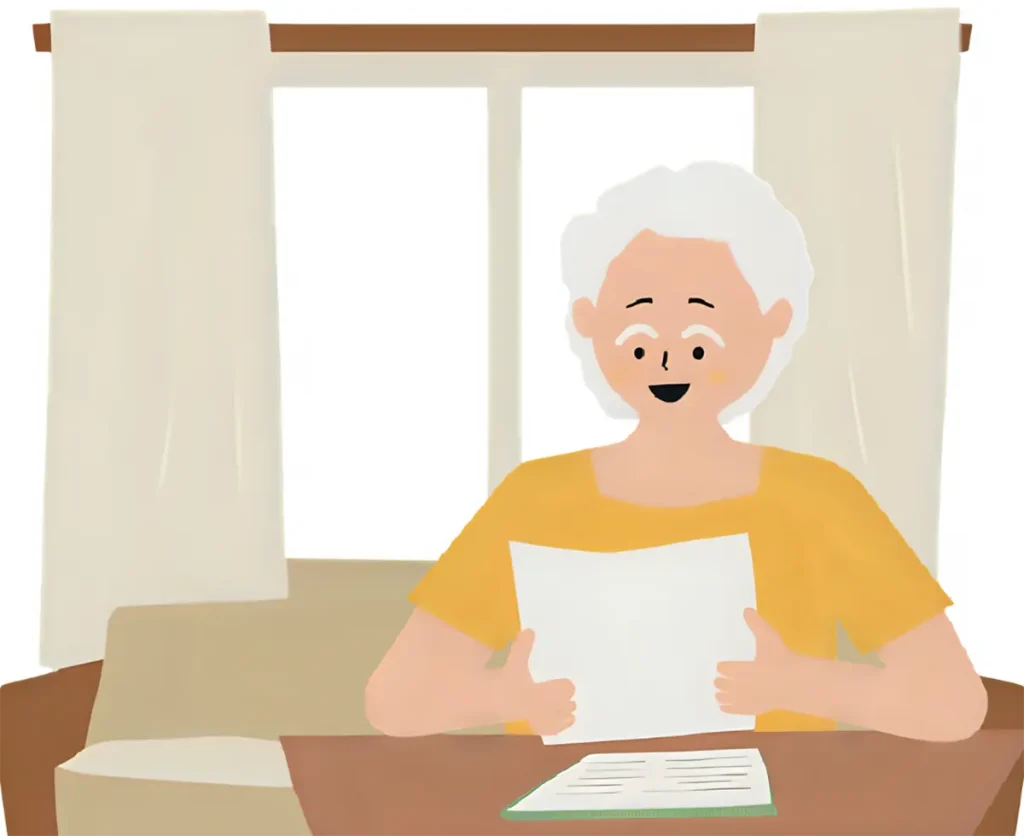


生前贈与とリビングウィル|今できる思いやりのかたち
「自分がいなくなったあと、家族は困らないだろうか?」
そんなときこそ、今のうちにできる“思いやりのかたち”を残しておきたいものです!
生前贈与とリビングウィルは、そのための心強い味方……。
実はこのふたつ、どちらも「これからの自分」と「これからの家族」のために使える、大切な準備なんです。
生前贈与|“今”を支える贈りもの
生前贈与とは、その名のとおり生きているうちに財産を誰かに贈ること。遺言や相続よりも早い段階で財産を分ける方法で、ちょっとした“今の応援”にもなるんですよ。
📌 たとえばこんなケースがあります
- 孫の進学費用に毎年100万円ずつ贈る
- 結婚資金や住宅購入を援助するためにまとまった金額を渡す
- 相続税対策として、少しずつ贈与しておく
つまり、生前贈与は想いを“今”届けられる手段なんですね。
📌 気になるの税金のイメージ…
| 贈与の内容 | 非課税の条件(2025年現在) |
|---|---|
| 一般贈与 | 年間110万円まで非課税 |
| 教育資金の一括贈与 | 孫などに1,500万円まで非課税(条件あり) |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 1,000万円まで非課税(条件あり) |
大切なのは、無理のない範囲で計画的に行うこと。必要なら、税理士や信頼できる専門家に相談してみてもいいですね。
リビングウィル|「自分らしさ」を託す意思表示
リビングウィル(尊厳死の宣言書)とは、延命治療や医療方針についての事前の意思表示のこと。病気や事故などで意思が伝えられなくなったとき、自分の考えを家族や医療者に伝えてくれる大切な書類です。
- 延命治療は希望しない
- 苦痛を和らげる処置を優先してほしい
- 自宅での看取りを望む など
ここで注目すべきは、リビングウィル=死に際の話ではないということ。むしろ、「どう生きたいか」を大事にするための宣言なんです。
- エンディングノートや専用の用紙を使うと◎
- 家族と事前に話し合っておくことが大切
- 医師や介護者にも共有しておくと安心
つまり、未来の自分に代わって“いまの自分”がメッセージを残すようなものなんですよ。
まずは気軽にできることから
- 家族と「お金や医療のこと、話しておきたいな」と切り出す
- 簡単なメモやノートに、気持ちを書き残しておく
- 「贈与ってどうだろう?」と調べてみる
こう考えると、“思いやりの終活”って案外むずかしくないんですよね。
ワンポイントアドバイス
生前贈与やリビングウィルは、単なる財産や医療の決定ではありません。それは、「今できる思いやり」の具体的なかたちなんです。特に、リビングウィルは、あなたが望む医療について事前に意思表示しておくことで、もしもの時にご家族が難しい判断を迫られる負担を軽減してあげられるんですね!
また、生前贈与も、生きているうちに感謝の気持ちとともに財産を渡せるのが魅力ですよね。つまり、これらの準備は、「家族を思いやる気持ち」なのですね!
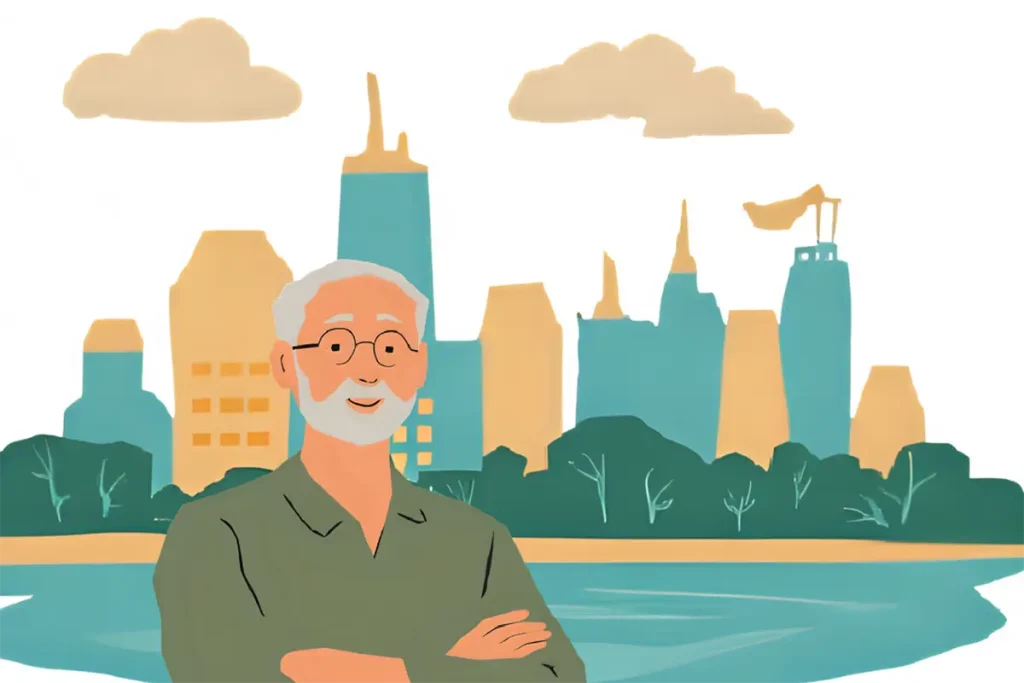
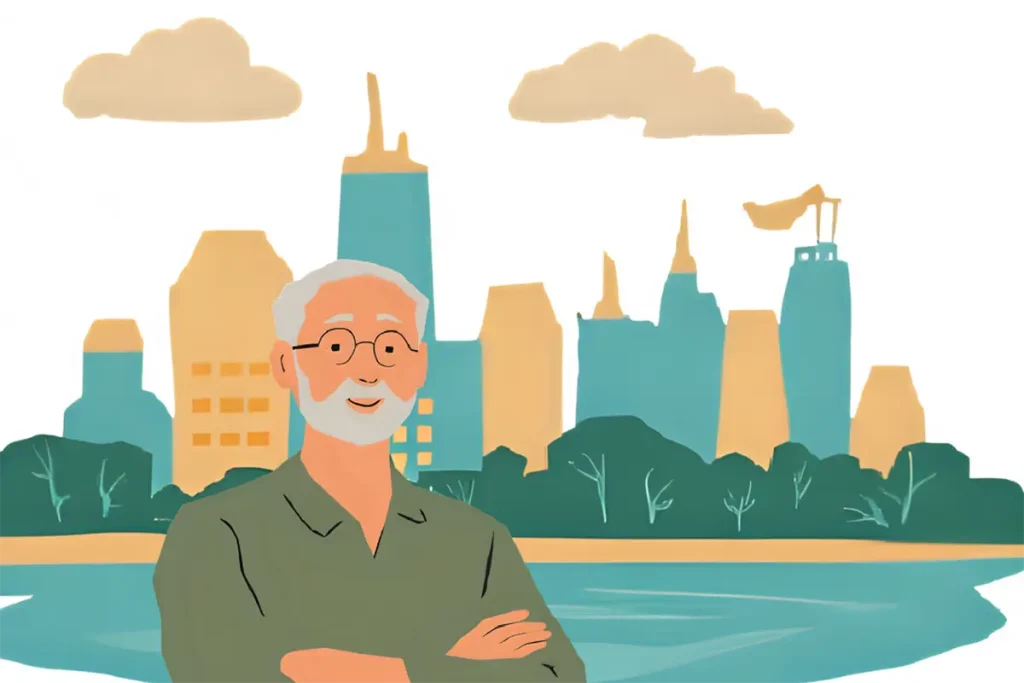


デジタル遺品の整理|スマホやSNSの終活対策
スマートフォンやSNS、ネットバンクにオンライン写真・・・。気づけば、私たちの大切な情報はほとんど“デジタル”の中にある時代になりました。それにもかかわらず、「デジタルのことまでは考えてなかった…」という声、実はとても多いんです。
つまり、“デジタル遺品”の整理は、これからの終活に欠かせないテーマなんですね。
デジタル遺品ってなに?|知らないと残された人が困ることも
まず、「デジタル遺品」とは、亡くなった後に残るスマホ・PC内のデータやインターネット上の情報のことです。
📌 たとえば、こんなものがあります。
- スマホやパソコンの中の写真・連絡帳・メモ帳
- メールやSNS(LINE、Facebook、X など)のアカウント
- ネット銀行・証券・ネットショップのIDやパスワード
- 有料サービスやサブスク契約(音楽・動画配信など)
📌 これらを放置してしまうと…
- 家族がログインできず、大事な写真や連絡が見られない
- 毎月の引き落としが続いて、無駄な支出が発生
- SNSアカウントがそのまま残り、不正利用のリスクも…
だからこそ、“自分で整理できるうちに整えておく”ことが、家族への優しさなんです。
整理のステップ|やさしく始める3つのコツ
📌 いきなり全部やろうとせず、できることから始めましょう。
| ステップ | やること | コツ |
|---|---|---|
| ① 書き出す | 利用中のサービスやアプリをリスト化 | メモ帳やノートでOK |
| ② パスワード管理 | パスワードの保管方法を決める | 紙のノート or 専用アプリ |
| ③ 伝える | 信頼できる人に管理方法を共有 | 家族 or 代理人に一言添えて |
意外かもしれませんが、この3ステップだけでも安心感がぐんと変わるんです。
エンディングノートと一緒に書くともっと安心
ここで注目すべきは、エンディングノートと一緒にまとめておくとより効果的ということ。以下のような内容を記入しておくと、ご家族も迷わず動けます。
- よく使うID・パスワード(のヒント)
- 「解約してほしいサービス」一覧
- SNSアカウントの削除希望の有無
- データの保存 or 削除の希望(写真・メッセージなど)
こうした情報があるだけで、家族は戸惑わず、スムーズに手続きができるんですよ。
今だからこそ、未来を軽くするチャンス
「まだ早いかな」と思う方もいるかもしれません。
でも、スマホやPCを使いこなしている“今”こそ、整えるチャンスなんです。
デジタル整理は始めてみると、実際のところ“今の自分のため”にもなります。
- パスワードを把握しておくと、日常の管理もスムーズに
- 不要なアプリを見直すことで、心もスマホもスッキリ
- 写真やメッセージを見返すうちに、思い出を再確認できることも
未来の安心は、いまの行動から生まれるんですね。
だからこそ、今こそ一歩踏み出してみてはどうでしょうか?
ワンポイントアドバイス
今の時代、スマホやパソコンの中には、私たちの生活の軌跡や大切な思い出がたくさん詰まっていますよね。しかし、その「デジタル遺品」の存在を忘れてならないのは、放置すると家族がログインできず、整理に困ってしまうことです。
そこで、特に目を引くのは、「IDとパスワードのリスト化」と「アカウントの整理」です。使用していないSNSやアプリは生前に解約し、必要なものは信頼できる家族にアクセス方法を伝えておくことが、デジタル終活の核となるんですよ。
こんな記事も読んでみてね!
介護と葬儀の備え|安心できる選択肢と事前準備
「介護」や「葬儀」のことって、どこか “まだ早いかな…” と思ってしまいがちですよね。
でも、ちょっとだけ準備をしておくと、大きな安心につながる分野なんです。
なぜなら、いざというときに「どうしたらいいの?」と迷わずにすむから・・・。
それは、“今の自分のため”にもなる終活のひとつなんですね。
介護の備え|「自分らしさ」を大切にする選択を
将来、介護が必要になったときのことを考えておくのは、とても現実的な備え・・・。
でも、決して暗い話ではありません。むしろ、「どう生きたいか」「どんな暮らしがしたいか」を考える前向きなプロセスなんですよ。
📌 まずは、以下のような選択肢を知っておくと安心です。
| 介護のかたち | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 自宅介護 | 家族のサポートを受けながら自宅で暮らす | ケアマネジャーや訪問介護の支援を活用 |
| 介護施設 | 有料老人ホーム・特養などを利用する | 希望条件は早めにリスト化 |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 比較的自立した方向けの住宅 | 元気なうちに見学がおすすめ |
要するに、「どんな暮らしを望むか」を見つめることが、介護の備えの第一歩なんです。
葬儀の準備|「残された人の安心」をつくる思いやり
一方で、葬儀に関する備えも、実は家族への最大のプレゼントだったりします。なぜなら、突然のときに「どう送ればいいの?」と悩まずにすむからです。
📌 押さえておきたいのは、以下のような項目です。
- 希望する葬儀スタイル(例:家族葬・一般葬・直葬)
- 宗教や宗派の希望
- お墓・納骨の方法(墓地・樹木葬・海洋散骨など)
- 葬儀社や事前相談の有無
- 呼んでほしい人・知らせたい人の一覧
ここで注目すべきは、事前相談が無料でできる葬儀社も多いということ。見積もりだけでも取っておくと、家族はとても助かりますよ。
エンディングノートでまとめておくと安心
介護や葬儀の希望は、エンディングノートに記しておくのが効果的です。書式は自由ですが、以下のような項目があるとより分かりやすくなります。
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 介護の希望 | 自宅か施設か、誰に相談したいかなど |
| 葬儀の形式 | 希望のスタイルや宗教、戒名の有無 |
| 連絡先 | 知らせてほしい人、喪主になってほしい人 |
| 費用のめど | 葬儀や納骨に使ってほしい預貯金の情報など |
つまり、大切な思いをカタチにしておくということなんですね。
ワンポイントアドバイス
実は、介護や葬儀の準備って、「自分らしく生きる」ための選択肢でもあるんです。
今から少しずつ考えておくことが、自分にも家族にもやさしい行動になるわけです。
「こんなふうに過ごせたらいいな」「こうして送ってほしいな」という思いが伝わるだけで、十分なんですよ。
だから、今の自分の気持ちを、そっと書き残してみませんか?
その一歩が、きっと未来の安心につながりますからね。




終活アプリと専門アドバイザー|60代からでも頼れるサポート術
終活は「すべてを自分ひとりでやらなければならない」と思っていませんか?
でも今の時代、便利なアプリや専門家の力を借りることで、無理なく前に進めるんです。
つまり、がんばりすぎずに、安心して終活に取り組める時代になってきたということなんですね。
終活アプリってどんなもの?
スマホがあれば、終活をやさしくサポートしてくれるアプリがたくさんあります。
紙のノートに比べて、すぐに更新できたり、バックアップが取れるのも嬉しいポイント。
📌 たとえば、以下のような機能があります。
| 機能 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| エンディングノート作成 | 自分の希望や大切な情報を入力 | いつでも見直せて、修正も簡単 |
| 財産・相続リスト管理 | 預貯金や不動産、保険などの記録 | 抜け漏れなく一覧にできる |
| 写真・メモ保存 | 家族へのメッセージや思い出を残せる | 想いを“声や画像”で伝えられる |
| デジタル遺品管理 | SNSやパスワードなどの記録 | 消し忘れやトラブルの防止に |
こうして見ると、「アプリってむずかしそう…」と思っていた方も、意外と便利だと思いませんか?
専門アドバイザーに頼るという選択肢
一方で、終活を進めるうちに「これは自分だけでは判断が難しいな」と感じる場面もあるかもしれません。
そんなとき頼りになるのが、終活の専門アドバイザーです。
📌 専門家に相談できる場には、次のような種類があります。
- 終活カウンセラー(資格者):終活全般を幅広くサポート
- 司法書士・行政書士:遺言や相続、財産管理に強い
- ファイナンシャルプランナー:生前贈与や老後資金の計画など
- 葬祭ディレクター:葬儀やお墓の具体的相談ができる
つまり、「どこに何を相談すればいいのか」がわかると、終活ってグッと身近になるんです。
アプリと専門家のいいとこ取りで、より安心に
📌 「アプリ」と「アドバイザー」をうまく組み合わせる方法…
- アプリでエンディングノートを作成 → 専門家に見てもらって内容を確認
- 財産情報をアプリで管理 → 相続時に士業のアドバイスを受ける
- デジタル遺品リストを作成 → ITに詳しい専門家と削除や整理を相談
このように、“手元のツール”と“プロの目”をバランスよく使うことで、自分らしい終活が形になっていくわけです。
ワンポイントアドバイス
終活って「全部一人でやる」ことじゃないんです。
大切なのは、“誰かに頼ってもいい”と思えることなんですよ。
便利なアプリや頼れる専門家を味方につけて、少しずつ進めてみてくださいね。
終活は「自分らしさ」と「安心」をつくる旅路・・・。
その旅に、よき伴走者がいれば、ずっと心強いはずです。
まずは、アプリを試してみるだけでもOK。
「これならできそう!」と思えることから、そっと始めてみてくださいね!!




60代からの“終活”で よくあるQ&A
60代は、これまでの人生を振り返り、これからの暮らしをより良く整えていくためのベストタイミング。「終活」とは決して暗いものではなく、心とモノをスッキリさせ、家族に安心を届ける前向きな行動です。
この記事では、終活の意味やタイミングから、断捨離・生前整理・エンディングノート・遺言・相続・デジタル遺品・介護・葬儀の備えまで、現代に合った実践的な方法をご紹介しました。
今から少しずつ動き始めることで、不安は希望に変わります。自分らしく、家族にも優しい最期を迎えるために――終活は、60代の今が「ちょうどいい」。さあ、あなたも今日から始めてみましょう。













