「認知症は仕方がないもの」と思っていませんか?実は、性格や日々の心の持ち方が、将来の脳の健康に大きく影響します。頑固さや孤立はリスクを高め、好奇心や笑顔は予防の力になります。本記事では、60代からでも実践できる“認知症になりにくい性格づくり”のヒントを解説。今からの小さな工夫で、未来のあなたの笑顔と自立を守りましょう。
認知症って予防できるの?|60代なら気になる性格との関係
60代を迎え、ふと「認知症」という言葉が頭をよぎることはありませんか?テレビやインターネットで目にしたり、友人や知人の話を聞いたりするうちに、自分ごととして気になり始める方も多いのではないでしょうか。でも、具体的に何をすればいいのか、そもそも予防なんてできるのか、不安に思っている方も少なくないはずです。
実は、認知症には「なりやすい性格」と「なりにくい性格」があると言われています。そう聞くと、「じゃあ、自分の性格は大丈夫なのかな?」ってちょっと心配になるかもしれませんよね。でも安心してください。これは決して、性格を変えなければならないという話ではありません。自分の心のあり方や、日々のちょっとした習慣が、脳の健康に深く関わっているというお話なのです……。
認知症と性格の関係って?
認知症と聞くと、老化や遺伝が原因だと考える方が多いかもしれません。しかし、近年の研究で、日頃の心のあり方や性格も、認知症のリスクに影響を与えることがわかってきました。特に、人生経験が豊富になる60代以降は、心の持ち方が脳の健康に大きな影響を与える時期だと言われています。
例えば、「新しいことを学ぶのは面倒だ」「もう年だから」と諦めがちな人は、脳への刺激が減ってしまいがちです。一方で、「あれもこれもやってみたい!」「もっと知りたい!」と好奇心旺盛な人は、常に脳が活性化している状態を保てます。この小さな違いの積み重ねが、将来の脳の健康に大きな差を生むのです。つまり、性格そのものを変えるのではなく、少し心のスイッチを意識的に変えてみることが大切だということなんですね!!
生活習慣病と同じなんです!
認知症は、生活習慣病と似ている部分がたくさんありそうです……。高血圧や糖尿病が、毎日の食事や運動不足の積み重ねで引き起こされるように、認知症もまた、日々の心の習慣が深く関係しているみたいなんです・・・。
| タイプの例 | 傾向 | 認知症リスクとの関係 |
|---|---|---|
| 神経質なタイプ | 物事を完璧にこなそうとし、小さなミスも気にしてしまう。 | ストレスを感じやすく、脳に負担がかかる傾向があります。 |
| 几帳面なタイプ | 決まったことを毎日同じように繰り返すのが好き。 | 新しい刺激が少なくなり、脳が活性化しにくくなることがあります。 |
| 内向的なタイプ | 人と接する機会が少なく、一人で過ごすことが多い。 | 社会的な交流が減り、脳への良い刺激が不足しがちになります。 |
これらの性格は、決して悪いことではありません。ただ、少しの工夫で、もっと脳に良い習慣を取り入れられるということなんです。例えば、完璧主義な方も、時には「まあ、いいか」と肩の力を抜いてみましょう。そうすることで、心も脳もリラックスできるはずです。
ワンポイントアドバイス
実は、認知症を予防する鍵は、すでにあなたの心の中にあるのかもしれません。大切なのは、「もう年だから」と諦めず、「まだこれから」と前向きに捉えることなんです。次の章では、具体的な「なりやすい性格」と、それをどう活かしていくかについてお話ししますね。


認知症になりやすい性格の共通点|諦めず、柔軟な心で向き合う方法
認知症になりやすい性格の共通点とは?
📌 研究から見えてきた傾向には、次のような特徴があります。
- 心配性・不安を抱えやすい → ストレスがたまり脳に負担がかかる
- 消極的で人との交流が少ない → 刺激不足で脳が活性化しにくい
- 頑固で柔軟性がない → 新しい情報を受け入れづらい
- 完璧主義で自分を追い込みやすい → 心身に余裕がなくなる
つまり、気持ちの持ち方や人との関わり方が、脳への刺激量やストレス耐性に影響しているんです。
表で見る「性格とリスクの関係」
| 性格の特徴 | 脳への影響 |
|---|---|
| 心配性・不安が強い | 慢性的なストレスで脳疲労が進みやすい |
| 人付き合いを避けがち | 会話や交流不足で刺激が少なくなる |
| 頑固で変化を嫌う | 脳の柔軟性が失われやすい |
| 完璧主義で自分に厳しい | 心の余裕を失い、脳が休まらなくなる |
性格の「クセ」がそのまま脳の負担につながっていることがわかりますよね。
柔軟な心で向き合う工夫
大切なのは「自分はダメな性格なんだ」と落ち込まないことです。むしろ、気づいたときが改善のチャンスなんです。例えば…
- 「心配性」 → 深呼吸や散歩でリラックスを心がける
- 「消極的」 → 近所の人にあいさつするなど小さな交流を増やす
- 「頑固」 → 新しい趣味に一歩だけチャレンジする
- 「完璧主義」 → 7割できたらOKと自分に言い聞かせる
ちょっとした意識の転換が、脳を守る大きな力になるんですよ!
ワンポイントアドバイス
完璧に性格を変える必要はありません。大切なのは「少し柔らかくする」ことです。例えば「今日は人に笑顔を見せてみよう」そんな小さな一歩で十分です。積み重ねれば、脳も心も自然と元気になっていきますから・・・。
性格は運命じゃなくて、日々の選択で育てていけるんです。だからこそ、あきらめずに柔軟な心で向き合ってみましょうね!


認知症になりにくい性格の秘訣|好奇心と社会性を育む習慣
認知症は「年齢とともに避けられないもの」と思われがちですが、研究では日常の性格や行動習慣が発症リスクに影響することがわかっています。特に「好奇心」「社会性」「柔軟な心」を大切にしている人は、脳のネットワークを活発に保ちやすく、結果的に認知症になりにくい傾向があるのです。
では、前の章で触れた「なりやすい性格」と「なりにくい性格」の違いを表で整理してみましょう。
認知症になりやすい性格 vs なりにくい性格
| 項目 | なりやすい性格 | なりにくい性格 |
|---|---|---|
| 思考の傾向 | 物事を悲観的にとらえがち | 前向きに受け止め、工夫して楽しむ |
| 人付き合い | 関係が狭く、孤立しやすい | 人との交流を楽しみ、広げようとする |
| 挑戦心 | 新しいことを避け、現状維持 | 好奇心を持ち、新しい体験を楽しむ |
| 感情表現 | 我慢や不満を抱え込みやすい | 素直に表現し、人に相談できる |
| 生活習慣 | 単調で刺激が少ない | 趣味や運動など変化を取り入れる |
このように、認知症リスクを下げる性格の共通点は「脳に新しい刺激を与え続けること」と「人との関わりを大切にすること」にあります。
好奇心と社会性を育むための習慣
- 日常に小さな挑戦を加える
- 新しい料理を作ってみる、普段と違う道を散歩するだけでも脳に刺激になります。
- 人との会話を楽しむ
- 近所の人にあいさつする、友人に近況を話すなど、社会性が脳を活性化します。
- 学びを続ける
- 本を読む、パソコンやスマホを学ぶ、カルチャースクールに通うなど、「知的好奇心」を持ち続けることが効果的です。
ワンポイントアドバイス
「大きな変化」よりも「小さな新しい体験」を積み重ねることが、脳の健康を守る近道です。
こんな記事も読んでみてね!
思考パターンを変えてリスクを減らす|ネガティブ思考をポジティブに変えるヒント
「性格は変えられない」と思いがちですが、実は思考のパターンを少し工夫するだけで脳の健康リスクを減らせることがわかっています。とくにネガティブな受け止め方をほんの少しポジティブに変えるだけで、気持ちが軽くなり、脳へのストレスも減っていくのです。そんな、考え方を整えることこそが、認知症予防の近道だったわけです……。
ネガティブ思考とポジティブ思考の違い
📌 まずは、よくある思考のパターンを比べてみましょう。
| 状況 | ネガティブ思考の例 | ポジティブ思考の切り替え例 |
|---|---|---|
| 人と会話した後 | 「うまく話せなかった…」 | 「次はもう少し伝えられそう!」 |
| 忘れ物をした時 | 「自分はダメだな…」 | 「次はメモしておこう!」 |
| 新しいことを勧められた時 | 「難しそうで無理かも…」 | 「ちょっと試してみるのもいいかも!」 |
こうして見ると、ほんの一言変えるだけで気持ちの軽さが全然違いますよね。
ポジティブに切り替えるコツ
📌 思考を変えるのは一気にではなく、「小さな工夫」を重ねるのがポイントです。
- 言葉をやさしく置き換える
- 「できない」→「まだ練習中」
- 失敗を学びに変える
- 「失敗した」→「次に活かせる経験」
- 人と比べない習慣を持つ
- 「自分は遅い」→「自分のペースで進めばいい」
物事を「完璧にこなすこと」よりも「前に進もうとすること」が大切なんですね!
日常でできる簡単トレーニング
- 1日の終わりに「今日よかったこと」を3つ書き出す
- できたことを小さくても自分でほめる
- 誰かと話したときに「ありがとう」を添える
積み重ねるうちに、自然とポジティブな思考が育っていきますから・・・
ワンポイントアドバイス
ネガティブをなくす必要はありません。むしろ「気づいたら少し言葉を変えてみる」だけで十分なんです。だから、焦らずに自分のペースで続けてみましょうね!




ストレスと上手に付き合う|心の負担を減らす思考の切り替え術
日常生活において、ストレスは避けて通れない存在です。特に人生中盤以降からは、仕事や家庭、将来の不安など、心に重荷を感じやすい時期でもあります。ここで大切なのは「ストレスをなくす」ことではなく、「ストレスと上手に付き合う」視点を持つことです。先ほどの「思考の切り替え」を、さらに生活習慣として取り入れていくことで、心の健康を守りやすくなります。
ストレスに強い人の思考パターン
- 出来事を「事実」と「解釈」に分けて考える
- 悪い部分だけでなく「プラスの側面」も探す
- 「完璧でなくてもいい」と自分を許す
こうした思考パターンを持つ人は、ストレスを感じても心のダメージが少なく、回復も早いのが特徴です。
ストレスを和らげる習慣
- 小さな楽しみを生活に散りばめる
- 音楽を聴く、散歩する、趣味に没頭するなど、自分がホッとできる時間を意識して作りましょう。
- 感情を言葉にして外へ出す
- 「疲れた」「しんどい」と口にするだけで、気持ちは少し軽くなります。信頼できる相手に話すことも効果的です。
- 思考を未来に向ける
- 「今できることは何か」にフォーカスするだけで、不安が希望に変わる瞬間があります。
ワンポイントアドバイス
ストレスを「悪者」と考えるのではなく、「うまく流す工夫を見つける」ことが心の柔軟性を育てます。呼吸を深くする、景色を眺めるなど、小さな切り替えが積み重なって大きな安心につながりますよ。




新しいことに挑戦する心|脳を活性化させる学びの力
年齢を重ねると、どうしても「新しいことは大変そう」と感じがちですよね。けれども、実は小さな挑戦こそが脳にとって最高の栄養なんです。新しい経験を積み重ねるたびに、脳の神経細胞は刺激を受けてつながりを強めていきます。つまり「慣れた毎日」よりも「ちょっと新しい毎日」のほうが、脳はずっと元気でいられるんです。
なぜ挑戦が脳にいいのか?
挑戦といっても、大げさなことをする必要はありません。むしろ、生活に少しだけ新しい工夫を加えることが大切です。
- 新しいことを学ぶと「記憶力・集中力」が鍛えられる
- 初めての体験は「ドキドキ」があり、脳に良い刺激を与える
- 成功体験は「自己肯定感」を高め、不安を和らげる
挑戦は心にも脳にも二重のプラス効果をもたらしてくれるわけです。
取り入れやすい小さな挑戦
📌 意外と身近なことでも「新しい挑戦」になりますよ。
- 普段行かない道を散歩してみる
- 簡単な料理に新しい食材を取り入れる
- 興味のある本を一冊だけ読んでみる
- スマホで写真を撮ってみる
- 新しい人に「おはよう」と声をかけてみる
ちょっとした変化でも「やってみた!」という気持ちが、脳をいきいきさせるんです。
「慣れた生活」と「挑戦する生活」の違い
| 生活のスタイル | 脳への影響 |
|---|---|
| 慣れたことだけを繰り返す | 脳の働きがマンネリ化しやすい |
| 小さな挑戦を取り入れる | 脳の神経回路が広がり、活性化する |
こうして比べてみると、ほんの少し挑戦を加えるだけで大きな違いがあることがわかりますね!
ワンポイントアドバイス
「新しいこと=特別なこと」と考えなくても大丈夫です。日常の中にある小さな工夫を楽しむことが、挑戦の第一歩なんです。つまり、焦らずに「ちょっとやってみようかな」という気持ちを大切にすればいいんですよ。
こんな記事も読んでみてね!
感謝と笑顔で満たす毎日|幸福感がもたらす脳への良い影響
「ありがとう」と口にしたり、自然に笑顔がこぼれたりする瞬間ってありますよね!!
実は、そうした前向きな感情は脳にとって大切なエネルギー源なんです。幸福感を感じると、ストレスが和らぎ、神経細胞の働きも安定するみたですよ!
だから、笑顔や感謝の習慣は、認知症予防にとって自然で心地よい方法だったわけです。
感謝と笑顔がもたらす効果
📌 感謝や笑顔の習慣には、こんなにたくさんの良い影響があるんです。
- 気持ちが安定し、ストレスが減る
- 脳内の血流が良くなり、集中力が高まる
- 人とのつながりが深まり、孤独感が減る
- 前向きな出来事を記憶しやすくなる
つまり、感謝や笑顔は「脳と心の両方」を健やかに保つ万能の習慣なんですね!!
「感謝と笑顔」を取り入れるコツ
📌 毎日の中で無理なく続けられる工夫を考えてみましょう。
- 毎日の中で無理なく続けられる工夫を考えてみましょう。
- 朝起きたら「今日も目覚められたこと」にありがとう
- 食事のときに「作ってくれた人」「食材」にありがとう
- 誰かに会ったら、できるだけ笑顔であいさつ
こうした小さな積み重ねが、やがて大きな安心感や幸福感につながるんです。
感謝や笑顔の有無でこんなに違う
| 習慣の違い | 脳や心への影響 |
|---|---|
| 感謝や笑顔が少ない | ストレスがたまりやすく、孤独感を感じやすい |
| 感謝や笑顔を意識する | 脳がリラックスし、人間関係も円滑になる |
こうして比べると、笑顔や感謝の効果がよく見えてきますよね!
ワンポイントアドバイス
「ありがとう」をノートに一つ書き留めてみるだけでも効果があります。感謝の記録を続けていくと、自然と前向きな出来事に気づきやすくなり、笑顔も増えていくんですよ。
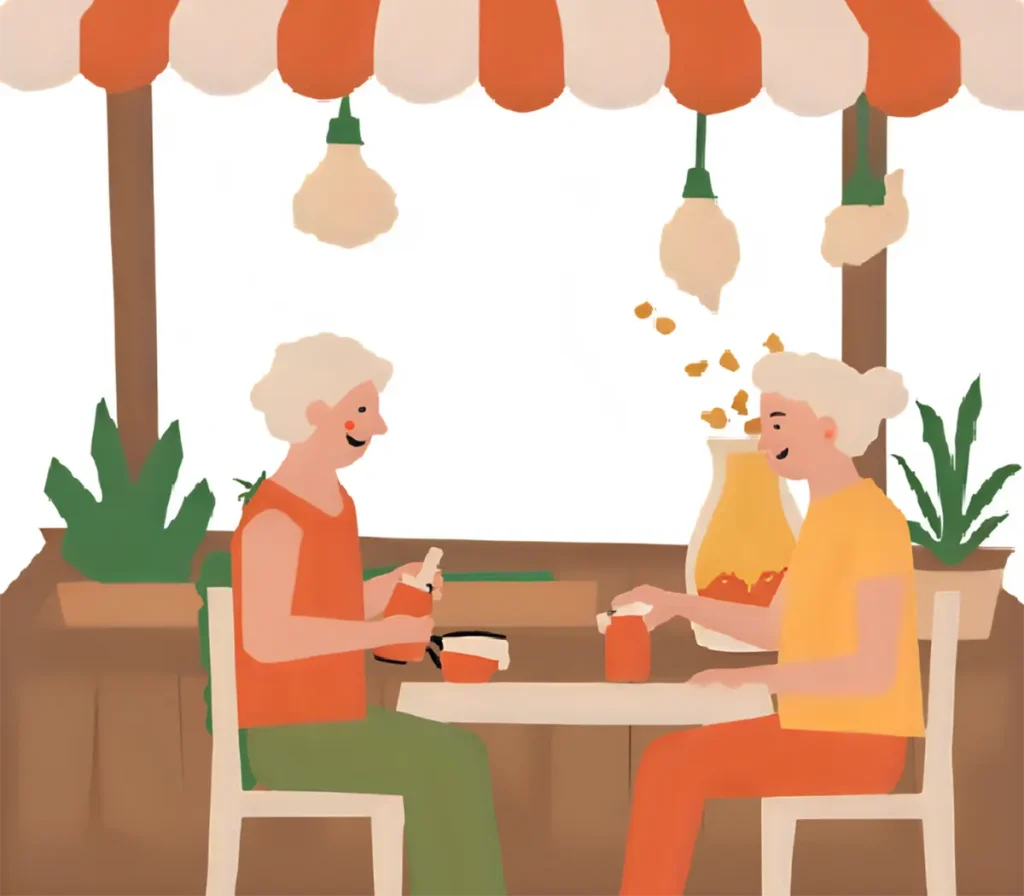
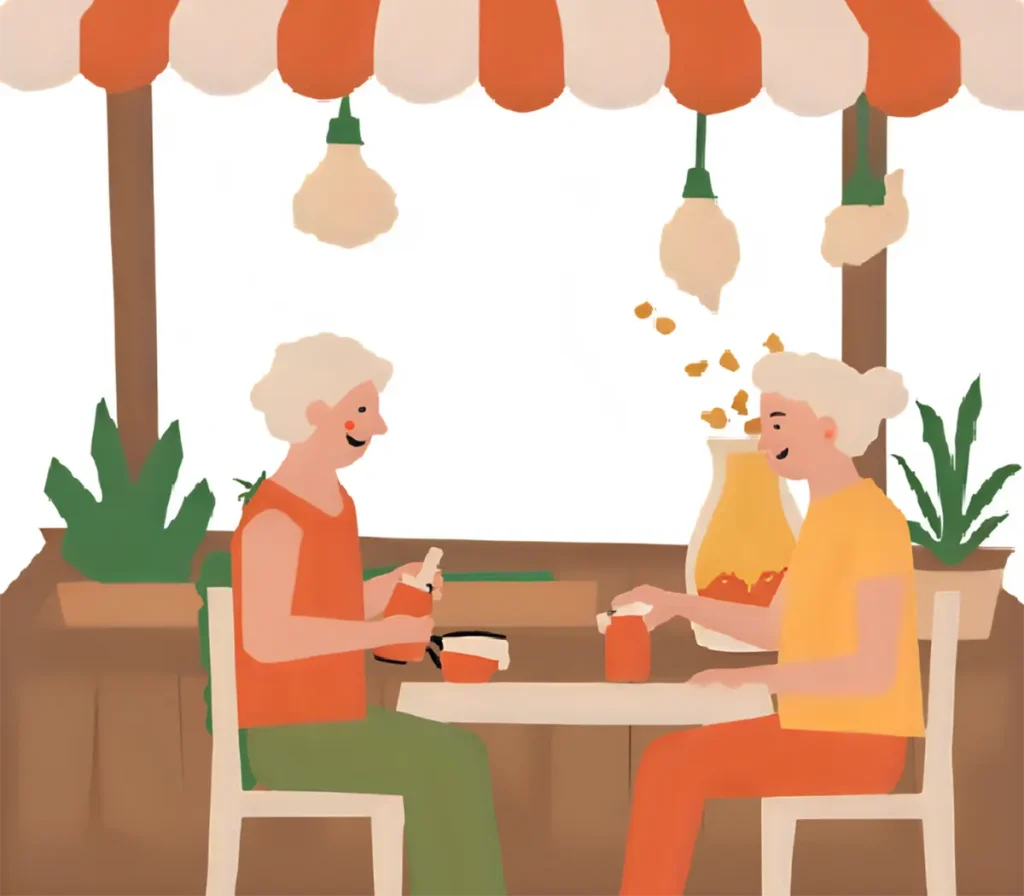


あなたらしい予防法を見つけよう|今日からできる行動と心の変化
ここまで見てきたように、認知症予防にはたくさんの方法があります。でも「どれが一番正しいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。実は、特別な正解はないんです。
なぜなら、人によって性格や生活環境が違うからです。だからこそ、自分に合ったやり方を見つけることが一番大切なんですよ。
あなたに合った予防法を探すヒント
同じことでも「楽しい」と思える人もいれば「ちょっと苦手だな」と感じる人もいます。大事なのは、無理なく続けられるスタイルを見つけることです。
- 好奇心がある方 → 新しい習いごとや本にチャレンジ
- 人と話すのが好きな方 → サークルや地域活動に参加
- コツコツ型の方 → パズルや日記で脳をコツコツ鍛える
- 体を動かすのが好きな方 → ウォーキングやダンスで気分転換
つまり、続けやすい習慣こそが、あなたの「最強の予防法」になるんです。
予防法の違いとメリット
| スタイル | 向いている人 | メリット |
|---|---|---|
| 学び型 | 知識欲がある人 | 脳の新しい回路が育ちやすい |
| 交流型 | 人が好きな人 | 孤独感が減り、気持ちが明るくなる |
| 習慣型 | コツコツ型の人 | 継続力が強みとなり、自信につながる |
| 運動型 | 活動的な人 | 脳と体の両方を健康にできる |
こうしてみると、自分に合ったスタイルが少し見えてきませんか?
今日からできる小さな一歩
📌 難しく考えず、日常の中に取り入れてみましょう。
- 朝起きたら深呼吸をひとつ
- 近所の景色を少し違う道で楽しむ
- コンビニでいつもと違う飲み物を選んでみる
- 会った人に「ありがとう」を言葉にしてみる
実はこれらも、立派な認知症予防なんです。ちょっとした変化が脳に新しい刺激を与えるからなんですね。
ワンポイントアドバイス
「完璧にやらなきゃ」と思う必要はありません。むしろ、「できそうなことを1つだけ」から始める方が長続きするんです。小さな積み重ねが、気づいたら大きな安心につながっているはずですよ。




今すぐ解決!認知症は性格で予防できる? に関する15の疑問
認知症は誰にとっても気になるテーマですが、「どうせ避けられない」と思う必要はありません。性格や心の習慣が脳の健康に大きく関わるからです。ネガティブ思考に偏らず、ストレスをためこまず、人との交流や新しい挑戦を楽しむ。これらの積み重ねが、脳を若々しく保つカギになります。
特別なことをしなくても「ありがとう」を伝える、笑顔で過ごす、好奇心を持つ。そんな日常の小さな選択が未来を大きく変えます。認知症予防は難しいものではなく、あなたらしい生活の中にこそ答えがあります。














