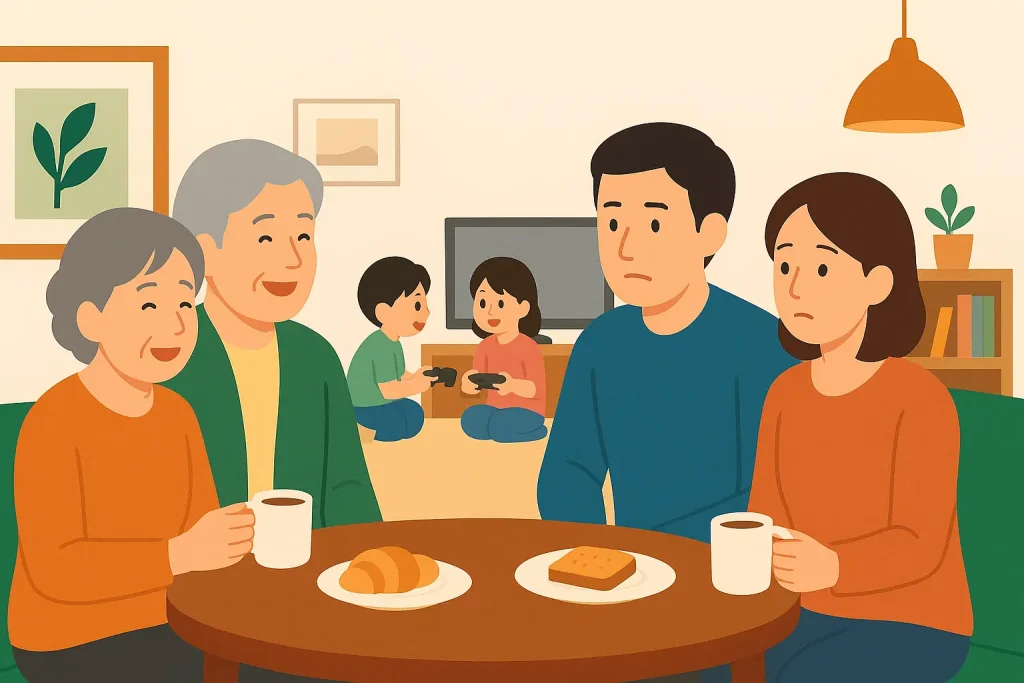「地震で助かったのに、その後命を落とすことがある」――それが災害関連死です。特に60代以上のシニア層は、体力や健康面の不安から被災後の環境に大きな影響を受けやすいのが現実。能登半島地震でも多くの高齢者が命を落としました。しかし、災害関連死は正しく備えることで防げる命でもあります。
近年では、大地震や線状降水帯、台風など思いもよらぬ大災害がどこで起こっても不思議ではありません。本記事では、災害関連死の定義や原因、事例を交えながら、シニア世代が今日からできる具体的な対策をわかりやすく解説しますね!
災害関連死とは|知っておきたい定義と見落とされがちなリスク
災害によって直接命を落とすわけではないけれど、その後の環境や体調の変化によって命を落としてしまう…。それが「災害関連死」と呼ばれるものです。たとえば避難所での生活による体力低下や持病の悪化、または心のストレスが引き金となるケースもあります。実はこの災害関連死、60代以上のシニア世代にとって、見過ごせない大きなリスクなんです。
災害関連死とは?
災害の発生から一定期間内に、避難生活や災害の影響で健康が悪化し、命を落とすケースを「災害関連死」と定義します。たとえば以下のような原因が挙げられます。
- 避難所での感染症・肺炎
- 持病の悪化(糖尿病・高血圧など)
- 冷えや脱水による体調不良
- 精神的ショックによる心不全や自殺
つまり、直接的な被害よりも「生活の変化」によるダメージが深刻になりがちなんです。
見落とされがちなリスクとは?
特にシニア層は、体力・免疫力の低下や持病を抱えている方が多く、以下のような状況で災害関連死につながりやすい傾向があります。
- トイレを気にして水分補給を我慢、脱水状態に
- 食事量が減って栄養失調になる
- 周囲との会話が減り、うつ症状が進行
- 医師や薬が足りず、慢性疾患が悪化
こうして見ると、目に見えにくい“静かなリスク”が潜んでいるとわかりますよね。
【事例】能登半島地震での災害関連死
たとえば2024年の能登半島地震では、高齢者の災害関連死が大きな社会問題となりました。避難生活の長期化や水・電気の不足、そして医療アクセスの制限が重なったことが原因とされているんです。
| 災害関連死の原因 | 説明 |
|---|---|
| 体調悪化 | 持病の再発・感染症・脱水など |
| 環境の変化 | 不眠・寒さ・不衛生な環境 |
| 心の不調 | ストレス・不安・孤独感 |
小さな備えが命を守る
だからこそ、今のうちからできる「小さな備え」こそが命をつなぐカギではないでしょうか!
- 持病のある方は「お薬リスト」を用意
- 冷え対策の防寒具を備蓄
- 家族や地域と連絡手段を確認
- 避難所の情報を事前に確認
災害関連死を防ぐには、災害が起きる前の「準備力」が大切なんです。
ワンポイントアドバイス
ここで注目すべきは、災害関連死は避難生活のストレスや環境変化が原因で命を落とすケースだという点なんです。特に見逃せないのは、持病の悪化やエコノミークラス症候群など、慣れない生活で体調が急変することなんです・・・。だからこそ、災害そのものへの備えだけでなく、「その後の生活」を見据えた準備こそが、本当に重要な対策なんです……。


能登半島地震の事例に学ぶ|災害関連死が増える本当の原因
「災害で命を落とす」というと、建物の倒壊や津波といった直接的な被害を思い浮かべがちですよね。でも実は、災害後に起こる“災害関連死”のほうが深刻になることがあるんです。能登半島地震では、特にシニア層の災害関連死が大きく報道されました。ここでは、その事例から「本当の原因」を探り、私たちが備えるべきことを一緒に考えてみましょう。
見えてきた3つの主な原因
能登半島地震では、被災地の過酷な状況の中、避難生活を続けることで亡くなった高齢者が多数報告されました。特に60代以上の方が多く、「命は助かったのに…」という切なさが残るケースが少なくなかったんです。
📌 災害関連死が増えた背景には、以下のような複合的な原因がありました。
- 持病の悪化:慢性疾患のある人が薬を切らし、治療できずに体調が悪化
- 寒さと不衛生な環境:暖房器具が使えず、低体温や感染症に
- 精神的ストレス:孤独・不安から食欲低下やうつ状態に
こうした「見えにくい危険」が、シニア世代に大きな影響を与えてしまったんですね。
能登半島地震における災害関連死の主なリスク
| リスク要因 | 内容 |
|---|---|
| 持病の悪化 | 医療機関の不足・服薬の中断 |
| 環境の悪化 | トイレ不足、避難所の寒さ、衛生環境の低下 |
| 心身のストレス | 孤独・不眠・情報不足からくる不安 |
| 支援体制の不備 | 高齢者や障害者への支援が行き届かず |
シニアこそ知っておきたい!災害関連死を防ぐ3つのヒント
ここで学べるのは、「命を守るには避難の先も考えることが大切」ということです。つまり、災害関連死を防ぐには、“生活の備え”が鍵になるんです。
📌 特に60代以上の方に意識してほしいのは次の3つ。
- お薬リストを用意しておく(薬の名前・用法をメモしておきましょう)
- 寒さ・冷えへの備え(毛布・カイロ・断熱シートは意外と重要)
- 誰かとつながる習慣(近所の方と声を掛け合うだけでも安心です)
このような小さなことが災害時には、大きな命綱になりますから・・・
ワンポイントアドバイス
能登半島地震の事例からわかるように、災害関連死が増える裏には「医療へのアクセス困難」という大きな問題が潜んでいます。つまり、普段ならすぐに治療できる病気や怪我も、避難所生活では悪化しやすいんです。だから、「自宅の備蓄だけで数日間の健康を維持できるか」という視点を持つことが、シニア世代にとって何よりも重要なポイントになってくるわけですね・・・。


シニアに多い災害関連死の要因|60代から注意すべき体調管理とは
60代に差しかかると、少しずつ体力や免疫力の衰えを感じる方も多いですよね。そんな年代だからこそ、災害後の体調管理は命に関わるほど重要なテーマなんです。実際に、能登半島地震などの大規模災害では、災害関連死の多くが60代以上のシニア層に集中していたという報告があります。
でも安心してください。気をつけるべきポイントを知っておくだけでも、リスクは大きく減らせるんですから・・・。
災害関連死につながる体調の変化とは?
避難生活が始まると、どうしても生活環境が一変してしまいます。睡眠不足や寒さ、ストレスなどが重なることで、体調を崩しやすくなるんです。特に次のような変化は、注意が必要なんですよ。
- 持病の悪化(高血圧・糖尿病・心疾患など)
- 足腰の弱りやすさによる転倒リスク
- 食欲不振・脱水・便秘などの消化器トラブル
- 精神的ストレスによる免疫低下
こうして見ると、健康な人でも避けられないリスクがたくさんあるんですよね。
60代以上に見られる災害関連死の健康リスク
| 健康リスク | 具体的な例・対策のヒント |
|---|---|
| 持病の悪化 | 常備薬を1週間分持ち歩く/お薬手帳の携帯 |
| 低体温・冷え症 | カイロ・毛布・レッグウォーマーで防寒対策 |
| 栄養不足・便秘 | 高カロリーの非常食・水・乳酸菌サプリを用意 |
| 転倒・骨折 | 滑りにくい靴・杖・簡易マットなどで転倒予防 |
| ストレス・不眠 | アロマ、アイマスク、イヤホンなどの安眠グッズ |
60代からできる体調管理のポイント
「ちょっとした不調」を放置しないことが大切なんです。とくに避難中は、無理をしすぎず自分の身体の声に耳を傾けることが、命を守る第一歩になるんですよ。
📌 次のような行動を、日常から少しずつ取り入れてみてくださいね。
- 毎日1回は自分の体調をメモしておく
- 簡単なストレッチを習慣にする
- 口にできる栄養食品(ゼリーや栄養バー)を備蓄しておく
- 冷え対策グッズを防災袋に入れておく
- 心配な持病は主治医と「災害時の対応」を相談しておく
事前に準備できることは意外とたくさんありますから・・・。
ワンポイントアドバイス
シニアに多い災害関連死の要因として、特筆すべきは「脱水症状」と「低体温症」なんです。特に避難所ではトイレを気にして水分摂取を控えてしまいがちですよね。しかし、これが血栓症などのリスクを高めるんです・・・。
シニアの方にとって、災害時の最大の敵は「我慢」かもしれません。無理をせず、まわりに助けを求める勇気も備えておきたいですね。
こんな記事も読んでみてね!
避難所生活がもたらすリスク|高齢者が直面する災害関連死の現実
大きな災害が起きた後、多くの人が避難所での生活を余儀なくされます。けれど、その避難生活が新たなリスクになることがあるのをご存じでしょうか?
特に60代以上のシニア世代にとって、避難所生活は災害関連死の大きな要因になりうるんです。
なぜなら、避難所は「安心」な場所であると同時に、「過酷な環境」でもあるからです。
実際、能登半島地震の事例では、避難生活中に体調を崩し命を落とす方が相次ぎました・・・。
なぜ避難所で体調を崩してしまうのか?
避難所の環境は、私たちが思っている以上に体に負担をかけます。特に高齢者にとっては、以下のようなリスクが重なりやすいんです。
- 寒さによる低体温
- プライバシーの欠如や騒音による不眠
- トイレの不自由さからの水分制限・脱水
- 段差や雑魚寝による転倒・骨折
- 持病悪化に対応できない医療体制
そうなんです。一つひとつは小さな問題でも、積み重なることで命に関わる事態になるんですよ。
| 主な原因 | 内容例 | 予防のヒント |
|---|---|---|
| 低体温 | 冷たい床、風通し、断熱性の低さ | アルミシート・カイロの準備を! |
| 睡眠障害 | 照明・音・周囲の話し声 | アイマスクや耳栓が意外と効果的です |
| 食事・水分不足 | 食べづらさやトイレを我慢して水分を控える傾向 | ゼリー食や経口補水液を用意しましょう |
| 感染症リスク | 空間の密集・換気不足 | マスクと消毒シートもあると安心です |
| 医療支援の不足 | 持病があっても医師が常駐していない避難所も | お薬手帳を防災袋に! |
災害関連死を防ぐには?避難所対策も準備のうち!
要するに、「避難所で生き延びる力」を身につけておくことが大切なんです。避難所での生活は、被災直後だけでなく、数日から数週間にわたることも珍しくありません。
📌 特に60代からは、以下のような備えがおすすめです。
- 携帯トイレ・水分補給アイテムの常備
- 床冷え防止のための断熱マットや銀マット
- 慣れた服薬スケジュールを守れるように薬のリストをメモ
- 「自分の居場所を確保するアイテム(毛布・タオル・間仕切り)」
- 日頃から地域の防災訓練に参加することで雰囲気に慣れておく
つまり、備えは「家の中」だけじゃなく、「避難所を想定すること」も大切な対策なんですよ。
ワンポイントアドバイス
避難所生活がもたらすリスクとして、何よりも重要なのは「環境の変化によるストレス」なんです。プライバシーの欠如や騒音は、睡眠不足や精神的な疲労を招き、持病の悪化につながりかねません。そこで考えるべきは、もし避難するなら、車中泊や親戚・知人宅への避難など、「在宅避難以外の選択肢」も事前に検討しておくことです。自分の体と心を守る選択肢を確保しておくことが鍵になるんです。




災害関連死を防ぐには?|60代からできる事前準備と対策
「災害関連死を減らすカギは “災害が来る前” の一手間にあるんです」。能登半島地震の事例を振り返ると、“直接のけが” ではなく、避難生活中に悪化した持病や低体温が主な原因で亡くなった方も多く見られました。つまり、60代以降のシニアがいま備えておけば、いざというときのリスクを大きく下げられるわけですね。
なぜ「事前準備」が命を救うのか
- 初動48時間は支援が届きにくい
- → 常備薬や水を“自分で”確保しておくことがポイントです。
- 体調は災害直後より数日後に崩れやすい
- → 寒さ・栄養・ストレス対策が、実は“後から効く”んですよ。
- 情報不足が判断ミスを招く
- → 普段から「どこに避難するか」「誰に連絡するか」を決めておくと安心です。
60代からそろえたい“命を守る10アイテム”
| カテゴリ | アイテム例 | ワンポイント対策 |
|---|---|---|
| 医療 | お薬手帳・1週間分の常備薬 | ジッパーバッグで防水保管 |
| 体温管理 | 断熱シート・貼るカイロ | 夜間の冷えを防いで低体温予防 |
| 水分・栄養 | 経口補水液・栄養バー | 「甘味+塩分」で脱水&低血糖を回避 |
| トイレ | 携帯トイレ10回分 | 水分制限をせずに済む“安心材料” |
| 情報 | 充電式ラジオ・モバイルバッテリー | 最新の避難情報をキャッチ! |
今日から始める3つの行動TIPS
- 週イチ防災見直しデーを設定
- 乾電池や食品の賞味期限をチェック。「気づいたら切れてた」を防ぎましょう。
- “ながらストック法”で負担ゼロ備蓄
- 普段飲む経口補水液や栄養バーを買い足し → 古い分から使う循環方式がラクなんです。
- 地域の顔なじみを増やす
- 町内会や趣味サークルに参加しておくと、災害時の「お互いさまネットワーク」が機能します。
ワンポイントアドバイス
「災害関連死とは備え不足が引き起こす二次的な死」とも言えます。
だからこそ、今すぐできる対策を一つでも多く実行しておくことが、あなた自身と周りの大切な人を守る近道なんですよ。
「今日、準備できた!」という小さな達成感を積み重ねて、いざというときに自信をもって行動しましょうね。




家庭でできる備え方|持病・服薬管理・冷え対策を見直そう
能登半島地震の事例から見えてきたのは、「災害関連死は自宅での備えの有無で大きく差が出る」という事実でした。特に60代以降のシニアは、持病悪化・低体温といった原因を抑える“ひと工夫”が、生死を分けるポイントになるんですよ。そこで今回は「家の中で今日からできる対策」を3つの視点で整理しました。
①持病と服薬を“見える化”する
- お薬手帳+緊急連絡カードを冷蔵庫に貼る
- 1週間分の薬を「朝・夕・寝る前」で小分けし、防水パックへ
- 家族や近所の友人に“服薬サポーター”をお願いし、災害時の飲み忘れを防ぐにはこれが近道です
②“あったか動線”で冷えをシャットアウト
- 断熱マットをベッド下とリビング椅子に敷く
- 電池式の貼るカイロを常にローリングストック
- 夜間トイレ用に厚手ソックスを枕元へ――これだけで低体温リスクは激減します!
③“ながら備蓄”で食事と水分をキープ
| 目的 | 目安量(3日分) | 具体例 | メモ |
|---|---|---|---|
| 水分補給 | 1人 9ℓ | 2ℓペット×4+経口補水液 | 高血圧でも安心な減塩タイプが◎ |
| 咀嚼がラクな主食 | 1人 9食 | レトルト粥・柔らかパスタ | 温め不要品を半分入れる |
| たんぱく質 | 1人 6食 | ツナ缶・豆パック | 開缶キー付きだと便利 |
ワンポイントアドバイス
家庭での備え方を見直す上で、特に目を引くのは「薬の備蓄」なんです。普段飲んでいる薬は、最低でも一週間分を非常用持ち出し袋とは別に保管しておくことが必要ですよ。そして、「冷え対策」として、アルミシートや使い捨てカイロを手の届くところに準備しておくことが大切です
今日できる小さな工夫を積み重ねて、次の災害でも笑顔でいられる毎日をつくりましょうね。
こんな記事も読んでみてね!
地域とつながる防災対策|孤立を防ぐための行動習慣とは
災害関連死の原因のひとつに、「孤立」があることをご存じですか?
特に60代以上のシニア世代は、体力や判断力の低下から避難が遅れがちになります。さらに、ひとり暮らしや高齢夫婦世帯では、災害時に頼れる人がいないことが多く、それが大きなリスクにつながるんです。
でも、だからこそできることがあるんですよ! 実際に能登半島地震の事例からも、日頃の「ご近所付き合い」や「地域とのつながり」が生死を分けたケースがいくつも報告されています。
“誰かとつながる”ことが、命を守る防災対策に
意外かもしれませんが、地域とのつながりは、最もシンプルで確実な災害関連死を防ぐには有効な対策のひとつなんです。
📌 たとえばこんな習慣が、災害時の「孤立」を防ぐきっかけになりますよ。
- 毎朝、顔を合わせる「見守りあい」
- 自治会や班のLINEグループへの参加
- 年に1回の防災訓練に参加して顔を覚えてもらう
- 近所の“助け合いカード”を冷蔵庫に貼る
顔見知りがいるかどうかで、いざというときの支援の届きやすさが大きく変わるわけです。
「つながり度チェック」で今の自分を見直そう
| チェック項目 | あてはまる |
|---|---|
| 隣近所に「困ったときは助けてね」と言える関係がある | ○ or × |
| 自治会や町内会に所属している | ○ or × |
| 避難所の場所とルートを知っている | ○ or × |
| 持病や服薬について伝えている人がいる | ○ or × |
| 災害時に連絡を取り合う相手が3人以上いる | ○ or × |
こうして見ると、「あ、ちょっと足りてないかも?」と思う項目があるかもしれませんね。でもまだ遅くはありません。今から始めればいいんです・・・。
“助け合い習慣”は、日常の中で育てられる
特別なことをする必要はありません。
まずは、小さな「声かけ」や「おすそ分け」から始めてみましょう。
- 夕方の散歩ついでに「こんにちは」とあいさつ
- 野菜が多く採れたらお隣に少しお裾分け
- 災害時の安否確認をお願いできる「もしもノート」を作る
人とのつながりは特別なことじゃないんです。
自然体で築いた関係こそが、いざというときの大きな支えになるんですよ。
ワンポイントアドバイス
孤立を防ぐための行動習慣として、実は意外なことに、「日頃のちょっとした挨拶」が鍵になるんですね!
普段から地域の住民と顔見知りになっていれば、災害時に声をかけやすく、安否確認がスムーズになりますよね。そこで浮かび上がるのは、自治体の「地域の見守り活動」や「防災訓練」に積極的に参加してみること。つまり、小さな交流の積み重ねこそが、災害時の大きな助けになるんです・・・。




心のケアも忘れずに|シニアのメンタル不調と災害関連死の関係
災害が起きたとき、私たちは、まず「身体の安全」を第一に考えますよね!
でもですよ…、実は心の健康も命を守るうえでとても大切なポイントなんです。
実際にメンタルのケアを怠ることで、災害関連死の原因になるケースもあることが分かってきました。
能登半島地震の事例でも、高齢者のうつ状態や孤独感からくる体調悪化が、多くの方に影響を与えていたと報告されています。
つまり、災害関連死を防ぐには、「心の備え」も欠かせないということなんです。
災害時のストレスがもたらす“見えない危険”
被災後、避難所や仮設住宅での生活は、環境の変化・人間関係のストレス・情報不足など、多くの不安要素に囲まれます。
その中で、特にシニア世代は次のようなリスクにさらされやすいんです。
- 環境の変化に慣れにくく、眠れなくなる
- 家族や友人との別れから、悲しみにふさぎ込む
- 会話が減り、孤独感や不安が積もっていく
- 持病が悪化しても、相談できずに我慢してしまう
こうした積み重ねが、やがて体調不良や服薬忘れにつながり、災害関連死の引き金になってしまうのです。
メンタル不調に気づくためのセルフチェック表
「自分は大丈夫」と思っていても、ストレスは静かに進行します。
そこで、次の表を使って自分の状態を少し見直してみましょう。
| チェック項目 | 最近の自分は? |
|---|---|
| 夜中に何度も目が覚めてしまう | ○ or × |
| 以前より食欲がなくなった、または過食してしまうことがある | ○ or × |
| 誰とも話す気になれない日が増えてきた | ○ or × |
| 毎日がなんだか無意味に感じる | ○ or × |
| 自分の気持ちを話せる相手がいない | ○ or × |
あてはまる項目が多い場合は、心の疲れがたまっているサインかもしれませんね。
「心の備え」は日常のなかで育てられる
では、どうしたらいいのでしょうか。
実は、特別なことをしなくても心のケアはできるんですよ。
- 一日一回、誰かと声を交わす
- 写真や音楽など“自分が安心できるもの”を非常袋に入れておく
- 気分が沈んだら、無理せず休むと決める
- 日記やメモに「今日のよかったこと」を書いておく
- 医師やカウンセラーに相談できる窓口を知っておく
こんなふうに、日頃のちょっとした習慣が、心の土台を整えることにつながります。
ワンポイントアドバイス
心のケアの面で何よりも重要なのは、「不安や孤独感を抱え込まない」こと・・・。災害によるストレスは、気づかないうちにメンタルに影響を与え、体調不良につながることもあります。
そこで着目すべきは、家族や友人との電話やメッセージで、日常の会話を続けること。つまり、「いつも通り」の感覚を維持することが、シニアのメンタルヘルスを守り、災害関連死のリスクを下げるための、非常に大切なケアになるんです。
体と同じように、心にも休養や助けが必要ということなんですね!




災害関連死の原因とシニアが備える対策で よくあるQ&A
災害による直接的な被害を免れても、その後の避難生活や医療環境の変化によって命を落とす――それが災害関連死です。
特に60代以上のシニアは、体力の低下や持病、冷え、孤独などさまざまな要因が重なり、命のリスクが高まります。しかし、事前にできる備えはたくさんあります。たとえば、持病の服薬管理の徹底、避難先での冷え対策、地域とのつながりを意識することなど。能登半島地震の事例からもわかるように、災害後の環境が健康に及ぼす影響は大きく、心のケアも欠かせません。
「助かった命を、守り抜くために」――この意識こそが、災害関連死を防ぐ第一歩です。今すぐ、自分や家族の備えを見直してみましょう。